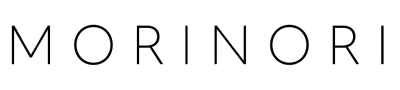平忠盛|平家物語巻第一『殿上闇討』現代語訳あらすじ
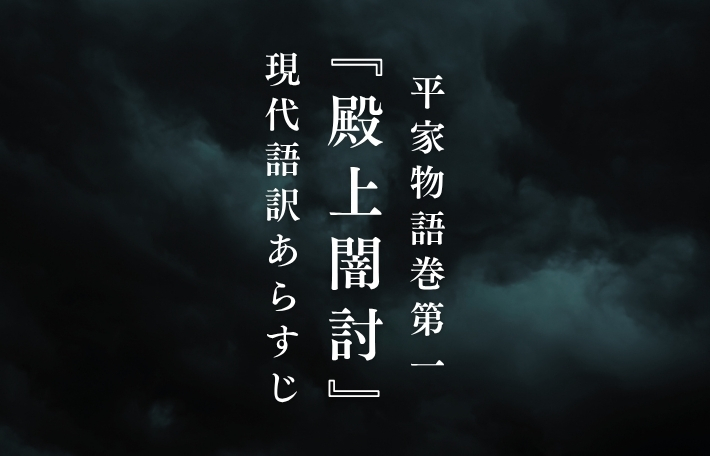
『殿上闇討』簡単なあらすじ
忠盛朝臣(平清盛の父)がまだ備前守であったころ、鳥羽上皇の御願によって得長寿院を建立し、その功績で但馬国を与えられ、ついに殿上への昇殿を許された。三十六歳にして初めて昇殿した忠盛を、公卿たちは武士の身でありながら昇殿を許されたことをねたみ、五節会の夜に闇討ちを企てる。忠盛はその噂を聞き、武士として恥を受けるまいと用心して参内。束帯の下に大ぶりの鞘巻を忍ばせ、闇の中で刀を抜いてみせた姿に、周囲は息をのむ。郎党の家貞も主人を守ろうと殿上の庭に控えていたため、不審に思われたが、その忠義ゆえに闇討ちは起こらなかった。その後、殿上人たちは「武士を殿上に召し入れ、自ら刀を帯びたのは無礼」と訴えるが、鳥羽上皇の詮議により、忠盛の刀は銀箔を貼った木刀であったことが明らかとなる。上皇は忠盛の慎みと用意周到さを褒め、罪には問わなかった。

平家物語巻第一『殿上闇討』現代語訳あらすじ
※平曲の譜面『殿上闇討』から書き起こした文章を現代語訳にしています
さて、忠盛朝臣(平清盛の父)がまだ備前守であった頃、鳥羽上皇の御願として得長寿院を造営し、三十三間の御堂を建てて、千一体の仏像を安置した。供養は天承元年三月十三日であった。その功により、朝廷からは「闕国(けっこく:国司不在の国)を賜うべし」との仰せがあり、たまたま空いていた但馬国が下された。上皇はなおもその働きぶりに深く感じ入られ、内裏への昇殿をお許しになった。忠盛は、三十六歳にして初めて殿上に昇る。
公卿(殿上人)たちはこれを妬み憤り、同じ年の十一月二十三日、五節豊の明の節会の夜、忠盛を闇討ちにしようと謀った。忠盛はこのことを聞き伝え、「私は文官ではない。武勇の家に生まれて、思いがけぬ辱めを受けるのは、一門にとっても我が身にとっても口惜しい。やむを得ん、身を全うして主君に仕えよという言葉もある」と言って、前もって用意を整えた。参内のとき、大ぶりの鞘巻をこしらえ、束帯の下にしどけなく差し、火の仄暗い方に向かってそっとこの刀を抜き、鬢にあてたところ、傍目には氷刃のように見えた。人々は皆、目をこらして見つめた。
また忠盛の郎等に、元は一門であった木工助・平貞光の孫、新三郎太夫家房の子にあたる左兵衛尉家貞という者がいた。薄青の狩衣の下に萌黄威の腹巻を着け、弦袋を付けた太刀を脇に挟み、殿上の小庭にかしこまって控えていた。蔵人頭をはじめ、皆怪しみ、「うつぼ柱より内、鈴の綱の辺りに、布衣(木綿の狩衣)の者が控えているとは何事か、狼藉である。すぐに立ち去れ」と六位を通じて伝えさせた。すると家貞はかしこまって申し上げた。「先祖代々お仕えする備前守殿が今夜闇討ちに遭われるとの噂を聞き及び、その成り行きを見届けようと控えております。立ち去るわけにはまいりません」と。これを無用とでも思ったのか、その夜の闇討ちは起こらなかった。
また、忠盛が御前に召されて舞を舞ったとき、人々は拍子を変えて「伊勢平氏はすがめ(斜視)なりけり」と囃した。恐れ多いことながら、この平氏の人々は、桓武天皇の御末とは申しながら、中期には都に住むことも少なくなり、地下の身分となって、伊勢国に長く住みついていたため、その国の名を取って「伊勢平氏」と囃された。そのうえ忠盛は目が少しかたよっていた(斜視であった)ので、そう囃されたのである。忠盛は何とすることもできず、御遊もまだ終わらぬうちに、そっと御前を退出しようとした。紫宸殿の裏にまわり、近くの殿上人が見ているところで主殿司を呼び、横差しにしていた腰の刀を預け置いて退出した。家貞が待ち受けていて、「いかがでございましたか」と尋ねたが、忠盛は、言えばそのまま殿上までも斬り込まんばかりの気迫であったので、「何もなかった」と答えた。
五節会では、白薄様の紙、濃染紙、巻上の筆、巴を描いた筆の軸など、さまざまに趣向を凝らして歌い舞うのが常であった。昔、太宰権帥の藤原季仲という人がいたが、あまりに肌が黒かったので「黒帥」と呼ばれた。この人がまだ蔵人頭であったとき、五節会で舞っていると、人々は拍子をそろえて「ああくろくろ、黒い頭、誰が漆を塗ったのか」と囃した。また花山院の前太政大臣・藤原忠雅公が十歳のとき、父を亡くして孤児であったのを、中御門の藤中納言家成がまだ播磨守であった頃、娘婿として迎え華やかにもてなしていたが、この忠雅も五節会で「播磨米は木賊か椋の葉か、人の綺羅を磨くは」と囃された。昔はこのようなこともあったが、特に問題は起こらなかった。末の世はいかがあらん、と人々は不安を語り合った。
案のごとく五節会が終わると、殿上人一同が訴え出た。 「それ雄剣を帯びて公宴に列し、兵仗を賜って宮中を出入りするのは、みな格式の礼を守る綸命による先規である。然るを忠盛は年来の郎従と称して、布衣の武士を殿上の小庭に召し置き、自らも腰の刀を横差しして節会の座に連なる。両条とも希代未だ聞かざる狼藉である。罪は重く、免れがたい。すぐに殿上の札を削り、官を解き、停任すべきである」と。 上皇はこれを聞いて大いに驚かれ、忠盛を召してお尋ねになった。
忠盛が申し上げたのはこうである。「まず、郎従が小庭に控えていた件につきましては、まったく存じません。ただ近頃、人々が何やら謀っているとの風聞があり、長年仕えてきた家人がその罪を免れさせようと、私に知らせず密かに参っていたようです。止めようがなかった次第です。もし咎あるべくは、その者を取り調べるべきかと。次に、刀の件につきましては、主殿司に預けてあります。お召し出しいただき、刀の実否によって御沙汰をお決めください」と陳情した。
上皇はこの儀をもっともだとされ、その刀を召し出してご覧になると、鞘巻は黒く塗られていたが、中は木刀に銀薄を貼ったものであった。「当座の恥辱を逃れるために刀を帯びている形を見せつつも、後日の訴えを予期して木刀を備えていたその心くばりは、まことに見事である。武人たる者のはかりごとは、まさにこのようであるべきだ。また郎従が小庭に控えていたことも、武士の郎等の習いによるものであり、忠盛の罪ではない。」と上皇はかえって感心され、罪に問うことはなかった。
ご案内
演奏会で語る平曲を現代語訳にしています。
▶平家物語現代語訳一覧
平家琵琶の伴奏で平家物語を聞いてみませんか。
▶演奏会一覧
▶平曲を聞く