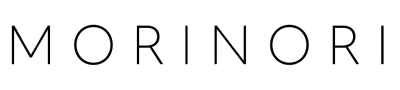琵琶ごとの違い

琵琶ごとの違い
平家琵琶は、『平家物語』の詞章を語る際の伴奏として用いられます。平家琵琶については以下のページをご覧ください。
▶平家琵琶について
琵琶にはいくつかの種類があります。こちらのページでは平家琵琶以外の琵琶について簡単にご紹介します。
薩摩琵琶(正派)
琵琶|四絃四柱(四本の絃に四本の柱)
薩摩琵琶は、島津忠久公が薩摩に入部する際、盲僧宝山検校を伴い伊作の常楽院を拠点としたことに始まります。以後、盲僧たちは島津家の祭祀や教化を担い、その演奏はやがて藩の士風教育と結びついていきました。
戦国期、島津忠良公(日新斎)は士人修養のために自ら和歌を詠み、寿長院に作曲を命じました。寿長院は桑の胴、凸型の表板、高い柱などを工夫し、現在の薩摩琵琶の形を整えます。また演奏法も、歌の句切れにのみ合の手を入れる方式を定め、士人が歌詞を吟じる際に伴奏できるよう設計しました。こうして島津歴代の庇護のもと、薩摩琵琶は武士の精神修養の一つとして受け継がれていきます。
第十七代の義弘公は兵庫頭忠平の名で「小敦盛」を作ったと伝えられています。さらに息子の家久公とともに朝鮮に出陣した際には、兵士の士気を鼓舞するために琵琶を携えました。各地で戦況を詩にし、弾奏を行ったことから端歌とともに戦記物が語られるようになり、やがて薩摩琵琶を象徴する奏法「崩れ」が生み出されました。
幕末には、さまざまな志士たちと薩摩琵琶にまつわる逸話が残されています。明治維新を経ると、鹿児島の奏者たちが関東へ赴いたことで、薩摩琵琶は広く知られるようになりました。
明治期に入り、永田錦心が技巧的な「錦心流」を確立すると、それ以前の古風な薩摩琵琶は「正派」と呼ばれるようになりました。正派は古風を守り、技巧を避け、高尚風雅を尊ぶことを理念とし、豪放で自由闊達な芸風を特徴とします。演奏は大きな撥で掻き鳴らし、即興的な変奏や雄叫びを交えるなど、迫力に満ちています。薩摩琵琶は「家元」「宗家」を立てず、各人が尊敬する師の芸風を学びつつ独自に工夫する伝統を持っています。
人物(一部紹介・他に大勢の方が居ます)
- 妙寿:幕末、盲僧でありながら流麗な技法を創始し「妙寿風」と呼ばれる。
- 徳田善兵衛:妙寿とともに妙楽の弟子。薩摩藩士であったが信仰による罪で町人となる。寺子屋で琵琶を指導したため町人の間に普及した。町風琵琶と言われたが元来武士である士風の本質を備えていた。
- 西幸吉:徳田善兵衛の高弟。西南の役に二十二歳で従軍。負傷して捕えられるも少年のため無罪放免となる。明治天皇・皇后の御前で吉水経水とともに演奏する。
- 児玉天南(利純):琵琶会の名目で京都二本松にある小松帯刀の別荘で、薩摩と長州の極秘の盟約が交わされた。そこで二十一歳の児玉利純が王昭君・小敦盛を弾奏したと伝わる。田原坂で負傷。
- 池田天舟(政徳):児玉天南の高弟。昭和37年に鹿児島県重要無形文化財に指定。
- 辻靖剛(号東舟):池田天舟の高弟。東京で義兄池田天舟とともに薩摩琵琶正絃会を組織し、多数の門弟を育て、日本琵琶楽協会設立にも尽力した。
薩摩琵琶(錦心流)
琵琶|四絃四柱
薩摩琵琶系統の一種である錦心流は、永田錦心氏によって明治三十年台に創設されました。少年期に薩摩琵琶の名手、家弓熊助氏の演奏を聴いたことがきっかけとなり、後に肥後錦獅氏や永江鶴嶺氏のもとで琵琶の技法を学んだ永田錦心氏は次第に頭角を現しました。当時の大衆に受け入れられる高度な琵琶楽を目指し、長唄など他の邦楽を参考にしながら様々な研究を重ね、優雅な響きを持つ錦心流を完成させたと伝えられています。錦心流は、技巧的で抒情性に富む点に特色があります。声と琵琶の掛け合いは緻密に整えられ、旋律も流麗に構築されています。
筑前琵琶
琵琶|五絃五柱 ※四絃もあり
筑前琵琶は、筑前盲僧を起源に持つ橘旭翁(橘智定)によって確立された流派です。嘉永元年に生まれた橘智定は明治二十五年に薩摩琵琶に感銘を受け、琵琶の改良に取り組みました。のちに橘旭翁と改名し、橘流筑前琵琶を組織して免許制度を導入しました。筑前琵琶は多彩な奏法を用い、さらに左手で音高を細やかに操作する繊細さを持ちます。語りと歌、琵琶の響きが一体となる表現が特徴で、薩摩琵琶が男性的・勇壮であるのに対し、女性的で優美と評されています。
錦琵琶
琵琶|五絃五柱
錦琵琶は、水藤錦穣によって創始された流派です。水藤錦穣は錦心流の榎本芝水に学び、永田錦心から直接の指導を受けたのち、女流演奏家が弾きやすいように薩摩琵琶から五絃五柱の錦琵琶を考案しました。錦琵琶は薩摩琵琶を改造し「女性的な華やかさ」を導入した点で画期的であり、女流演奏家の活躍の道を大きく切り開きました。
鶴田流琵琶
琵琶|五絃五柱
鶴田流は、鶴田錦史によって戦後に創始された流派です。鶴田錦史は錦心流から出発し、さらに錦琵琶を経て独自の芸風を打ち立て、鶴田流琵琶として琵琶を国際舞台に押し出した人物として知られています。古典演目から現代音楽まで幅広いレパートリーを有し、新たな表現領域を切り開きました。
※現在、薩摩琵琶鶴田流、あるいは薩摩琵琶と表記されることもありますが、当サイトでは鶴田錦史氏のご尽力と薩摩琵琶の歴史的経緯を鑑み、「鶴田流琵琶」と表記しています。
資料
琵琶についての説明は以下の資料を参照しました。
- 越山正三『薩摩琵琶』 薩摩琵琶同好会監修
- 島津正『江戸以前 薩摩琵琶歌』
- 日本琵琶楽協会編『創立50周年記念 日本琵琶楽協会のあゆみ』
- 金田一春彦『平曲考』