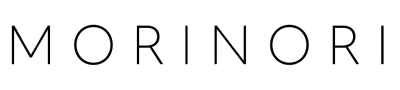平家物語|「ICHIMON26」インスタレーションノート

ICHIMON26|SAKAI-05 LIGHT
対象物に投じられる光、あるいは自然光によって立ち現れる光と影。その一瞬の移ろいの中に、忘却と記憶のあわいを描く。
『ICHIMON26|SAKAI-05 LIGHT』(2026)

今回のインスタレーションで用いたのは巻紙です。物語は巻七の後半にまとまっていますが、巻一から連なる流れを断ち切らないようフレームに巻きつける形にしました。物語の中で幾重にも結ばれてきた絆と、それを蹂躙する出来事は、途切れることなく続いていきます。その連なりの合間に、てのひらで握りしめたニュアンスを重ねました。

今回扱っているのは一門が都を落ちていく場面をめぐる物語群です。この先、平家一門が再び揃って都へ戻ることはありません。巻紙は破らなかったというより破れなかったと言うべきかもしれません。一門の終焉へと傾いていく様々な出来事ですが、握りしめて破ることはできませんでした。巻き付けた姿は巻物のようでもあり、蛇のようにも見えます。

床に配置した緩衝材は「飛沫」を表しています。ここまでに踏みしめられてきた命であり、これから先、一門の運命もまたこの「飛沫」の中に取り込まれ、あわいの彼方へと消化されていきます。
日光

このインスタレーションは光によって成立するため、完成した姿が現れるのは、日光が差し込むほんの一瞬です。日光が巻紙に投影され、物語が、都が、蛇の姿が、燃えているような表情を見せました。(平曲の撮影時は、シャッターを下ろした状態で行っています)



巻紙をフレームから外すと、巻紙は脱皮した蛇の皮のように見えました。蛇は地上で長い年月を生きると、やがて龍となり、空へ昇るのだといわれています。


| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制作時期 | 2025年11月 |
| タイトル | ICHIMON26 |
| シリーズ | SAKAI-05 LIGHT |
| コンセプト | 対象物に投じられる光、あるいは自然光によって立ち現れる光と影。その一瞬の移ろいの中に、忘却と記憶のあわいを描く。 |
| 素材 | 紙・ポリエチレン・その他 |
| 制作・演出 | 盛典(インスタレーション・撮影) |
| 語り | 盛典・雷伝(平家琵琶) |
平家物語現代語訳
巻七より
― 維盛都落
― 忠度都落
― 経正都落
― 青山
― 一門都落
平曲×インスタレーション

▲画面をクリックすると再生されます(音量にご注意ください)
時間|5分52秒
物語|平家物語巻第七『維盛都落』
詞章
御弟新三位の中将資盛、左の中将清経、同じき少将有盛、丹後の侍従忠房、備中の守師盛、兄弟五騎馬に乗りながら門の内へうち入れさせ庭に控へ大音聲をあげて「行幸は早遥かに延びさせ給ひぬらんにいかにや今までの遅参候ふ」と声々に申されたりければ、三位の中将馬に乗りながら既に出んとし給ふが、また引返し縁の際にうち寄せ弓の弭にて御簾をざつと掻き上げて「あれ御覧候へ幼き者共があまりに慕ひ候ふを兎角こしらへ置かんと仕るほどに、存の外の遅参候ふ」と宣ひも敢へずはらはらと泣き給へば、庭に控へ給へる一門の人々も皆鎧の袖をぞ濡らされける。ここに三位の中将の年来の侍に斎藤五斎藤六とて兄は十九弟は十七になる侍あり。

▲画面をクリックすると再生されます(音量にご注意ください)
時間|7分37秒
物語|平家物語巻第七『忠度都落』
詞章
薩摩の守「今は屍を山野に曝さば曝せ、憂き名を西海の波に流さば流せ、憂き世に思ひ置く事なし暇申して」とて馬に打乗り甲の緒を締めて西を指してぞ歩ませらる、三位後ろを遥かに見送つて立たれたれば忠度の声と思しくて「前途程遠し思ひを雁山の夕辺の雲に馳す」と、高らかに口号み給へば俊成卿いとど哀れに覚えて涙を押さへて入り給ひぬ。

▲画像をクリックすると再生されます(音量にご注意ください)
時間|4分04秒
物語|平家物語巻第七「経正都落」
詞章
旅衣夜な夜な袖をかたしきて思へば我はとほくゆきなん。さて巻ひて持たせられたりける赤旗ざつと差し上げたれば、あそこ此処に控へて待ち奉る侍共あはやとて馳せ集まりその勢百騎ばかり鞭を挙げ駒を早めてほどなく行幸に追つ付き奉らる。

▲画面をクリックすると再生されます(音量にご注意ください)
時間|10分08秒
物語|平家物語巻第七『青山』
詞章
彼青山と申す御琵琶は昔仁明天皇の御宇、嘉祥三年三月に掃部頭貞敏渡唐の時、大唐の琵琶の博士廉承武に逢ひ三曲を伝へて帰朝せしに、其時玄上、獅子丸、青山とて三面の琵琶を相伝して渡りけるが、龍神や惜しみ給ひけん、浪風荒く立ちければ獅子丸をば海底に沈めぬ、今二面の琵琶を渡いて我朝の帝の御宝とす。

▲画面をクリックすると再生されます(音量にご注意ください)
時間|15分57秒
物語|平家物語巻第六『一門都落』
詞章
落行く平家は誰々ぞ、前の内大臣宗盛公、平大納言時忠、平中納言教盛、新中納言知盛、修理の大夫経盛、右衛門の督清宗、本三位の中将重衡、小松の三位中将維盛、新三位中将資盛、越前の三位通盛、殿上人には内蔵頭信基、讃岐の中将時實、左の中将清経、同じき少将有盛、丹後の侍従忠房、皇后宮の亮経正、左馬の頭行盛、薩摩の守忠度、能登の守教経、武蔵の守知章、備中の守師盛、淡路の守清房、尾張の守清定、若狭の守経俊、経盛の乙子大夫敦盛、蔵人の大夫業盛、兵部の少輔正明、僧には二位の僧都栓真、法勝寺の執行能円、中納言の律師仲快、経誦坊の阿闍梨祐円、武士には受領検非違使衛府諸司の尉百六十人、都合その勢七千余人、これはこの三ヶ年が間東国北国度々の軍に討洩らされて僅かに残るところなり。
平大納言時忠の卿、山崎関戸の院に玉の御輿を舁居させ男山の方を伏し拝み、南無帰命頂礼八幡大菩薩願はくは君を始めまいらせて我等を今一度故郷へ帰し入れさせ給へと祈られけるこそ悲しけれ。おのおの後ろを顧りみたまへば霞める空の心地して煙のみ心細うぞ立ち上る。平中納言教盛、はかなしな主は雲井に別るれば宿は煙と立上るかな。修理大夫経盛、故郷を焼野の原とかえりみて末も煙の浪路をぞゆく。まことに故郷をば一片の煙塵に眺めつつ、前途万里の雲路に赴かれけん心の内推し量られて哀れなり。