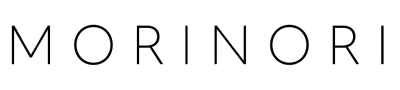平家琵琶について

平家琵琶は、『平家物語』の詞章を語る際の伴奏として用いられます。物語の伝承、供養の実践、そして音楽表現が一体となった、中世を代表する芸能です。「平家」「平家琵琶」「平曲」と表記する場合もありますが、当サイトでは混乱を避けるため「平曲」と表記しています。
平家琵琶と他の琵琶で語る違い
平曲の譜面は、詞章に沿って曲節が記されており、それに則って平家琵琶の伴奏とともに語られます。そのため他の琵琶では平曲を語ることができません。他の琵琶で演奏する平家物語は、物語の中から特定の場面や文章を取り上げ、それぞれの琵琶独自の節を付けて演奏しています。
琵琶には種類があります。魅力も多彩です。
▶琵琶ごとの違い
起源
『平家物語』は平家滅亡後、さまざまな人物や場所で編纂され、複数の異本が存在します。その成立には諸説があり、神社や寺院の縁起、ゆかりある土地の伝承、当時の親類縁者や歴史書に基づく語りが積み重なり、やがて一つの物語として形を成したと考えられています。
一説によれば、比叡山の慈鎮和尚(慈円)のもとに身を寄せていた藤原行長が執筆を始め、そこに僧侶や関係者の伝承が加えられました。雅楽に通じた行長と、天台声明に秀でた慈円が協力して物語を語り物の形に仕立て、それを生仏に語らせたことが、平家琵琶による語り物としての『平家物語』の起点になったと伝えられています。
こうした経緯を踏まえると、平家琵琶の起源は単一のものではなく、当初から多様なかたちで琵琶と結びつき、各地で語られてきたことがうかがえます。
中世の展開
生仏の後、如一と城玄が登場し、それぞれ一方流・八坂流を名乗って分派しました。南北朝期には名人明石覚一が現れ、足利尊氏の庇護を受けて平曲は最盛期を迎えます。覚一は音楽的内容を刷新し、その型が後代へと受け継がれたと伝わります。
衰退と記譜化
江戸時代に入ると、三味線音楽の隆盛に押され平曲は次第に衰退しますが、幕府の庇護もあって命脈は保たれました。この時期に学習用の記譜化が進み、名古屋の荻野知一検校『平家正節』は、前田流の伝承を墨譜で記したものとして知られています。
明治以降の動向
明治維新後、幕府の庇護を失った平曲は大きな打撃を受けました。前田流は名古屋や仙台の伝承者によって命脈を保ち、戦後の復興期には研究者による調査・記録とともに再び注目されました。現代では名古屋や仙台の系統の奏者や研究者たちが伝承を続け、学術的研究と芸能の双方から支えられています。
盛典が語っているもの
言語学者の金田一春彦氏は、仙台の館山甲午氏のもとでの学びに独自の研究を重ね、その成果「平曲考」をまとめました。金田一氏の口伝と研究資料は数人の奏者に引き継がれ、その一人が薩摩琵琶・平家琵琶奏者の須田誠舟氏です。
盛典は現在、須田誠舟氏のもとで学んでいます(須田氏のもとでは「伝承者」や「相伝」といった表現は用いられていません)。
平曲や平家琵琶は、神社やお寺、研究発表会以外では目にする機会が少ないかもしれません。伝統を守る方々に敬意を払いながら、盛典は学びの一環として小さな演奏会やインスタレーションを行っています。
資料
平家琵琶についての説明は以下の資料を参照しました。
- 越山正三『薩摩琵琶』 薩摩琵琶同好会監修
- 日本琵琶楽協会編『創立50周年記念 日本琵琶楽協会のあゆみ』
- 金田一春彦『平曲考』