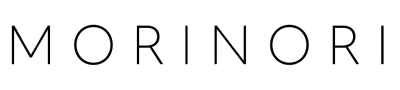平清盛|平家物語巻第六『入道逝去』現代語訳あらすじ

平曲|入道逝去(にゅうどうせいきょ)

▲画面をクリックすると再生されます(音量にご注意ください)
時間|6分01秒
物語|平家物語巻第六『入道逝去』
詞章
閏二月二日の日、二位殿熱さ堪へ難けれども日に沿て頼み少ふ見え給へば、御枕により泣く泣く宣ひけるは、「それ何事にてもあれ、思召れんずる御事あらば、物の少し覚えさせまします時、仰せられ置け」とぞ宣ひける、入道相国日来はさしも勇々しうおはせしかども、今はの時にも成りぬれば世に苦しげにて息の下にて宣ひけるは、「当家は保元平治より以来、度々の朝敵を平らげ勧賞身に余り、忝くも一天の君の御外戚と成つて丞相の位に至り栄華既に子孫に遺す、思ひ置事とては今生に一つもなし、但し思ひ置事とては入道が一期の中に頼朝が頭を見ざりける事こそ口惜けれ、我いかにもなりなん後仏事孝養をもすべからず、又堂塔をも建つべからず、先鎌倉へ討手を遣はして頼朝が首を斬つて、我墓の前にかけさせよ、それぞ思ふ事よ」と宣ひけるこそ恐しけれ、もしや助かると板に水置てふしまろび給へども、少しも助か給ふ心地もし給はず、同じき四日の日、悶絶躃地して、終ににあつち死にぞし給ひける。
平家物語巻第六『入道逝去』現代語訳あらすじ

※平曲の譜面『入道逝去』から書き起こした文章を現代語訳にしています
同じ二十三日、院の殿上において、急に公卿たちの詮議が行われた。前の右大将・宗盛卿が申し上げたのは、「先年、坂東へ追討の兵を差し向けたとは申せ、これといった成果もございませんでした。今度は宗盛が命を承り、東国・北国の凶徒どもを追討いたしたく存じます」ということであった。諸卿は顔色を改め、「宗盛卿の申されるところは、まことに勇ましい」と口々に述べた。法皇はこれを大いに喜ばれ、公卿も殿上人も、武官である者、少しでも弓矢に携わるほどの者は一人も残らず、皆、宗盛卿を大将軍として、東国・北国の凶徒を追罰せよと仰せ下された。
同じ二十七日、出陣のため門出しいよいよ出発しようとしたが、夜半ごろから入道相国(平清盛)が急に体の具合を悪くし、その日の出陣は取りやめとなった。翌二十八日、入道が重い病に伏したと聞くと、京中や六波羅では、「これは、ついにその時が来たのではないか」と、人々がひそひそと囁き合った。病に伏してからというもの、湯も水も喉を通らず、体の内は火を焚くように熱く、口にされる言葉といえば「あつい、あつい」と言うばかりであった。横たわっている場所から四、五間ほどの内へ入る者も、その熱さに耐えられなかった。
あまりの耐え難い熱さに、比叡山から千手井の水を汲み下ろし、石の舟に満たしてその中に入れて冷やそうとしたが、水はたちまち沸き立ち、ほどなく湯となった。もしやと思い、筧から水を注がせると、焼けた石や鉄に水をかけたように水は弾け飛び、触れた水は炎となって燃え上がり、黒煙が殿中に満ち、炎が渦を巻いて立ち上った。これは昔、法蔵僧都という人が、閻魔王の招きに応じて母の生所を訪ねた折、閻魔王の憐れみにより獄卒を添えられ、焦熱地獄を見せられたという話に似ている。鉄の門の内に入って見ると、流星のように炎が空に立ち上り、その高さは数百由旬にも及んだというが、今の有様もそれに劣らぬほどであった。
また、入道相国の北の方八条の二位殿がご覧になった夢も、まことに恐ろしいものであった。激しい火に包まれた車が、主もなく門の内へ引き入れられていく。二位殿が「これは、どこから来た車か」と問われると、「閻魔王宮より、平家太政入道殿のお迎えでございます」と答えた。車の前後に立つ者を見ると、ある者は牛の面のようであり、ある者は馬の面のようであった。車の前には、「無」という字だけがはっきりと現れた鉄の札が立てられていた。二位殿が「あれは何の札か」と問われると、「南閻浮提にある金銅十六丈の盧遮那仏を焼き滅ぼした罪によって、無間の底に沈むべき旨が、閻魔の庁で裁定されました。そのため『無間』の『無』だけが記され、『間』の字はまだ書かれておりません」と答えた。二位殿が夢から覚め、このことを語られると、聞く者は皆、身の毛もよだつ思いがした。霊仏・霊社へ金銀七宝を捧げ、馬、鞍、鎧、兜、弓矢、太刀に至るまで運び出して祈願したが、その効験はなかった。ただ男女の公達たちが枕元に集まり、嘆き悲しみ合うばかりであった。
閏二月二日、二位殿は清盛の熱さがいよいよ耐え難く、日を追うごとに回復の望みが薄れていくのを見て、枕元に寄り、泣く泣く言われた。「どのようなことでも、心残りに思われることがあれば、意識のある今のうちにお聞かせください。」入道相国は、日ごろはあれほど勇ましく振る舞っていたが、最期の時が迫ると、苦しげな息の下で言った。「平家は、保元・平治以来、度々の朝敵を討ち平らげ、その恩賞は身に余るほどであった。恐れ多くも天皇の外戚となり、丞相の位に至り、栄華はすでに子孫に残した。今生に思い残すことは一つもない。ただし、この入道が生きているうちに源頼朝の首を見られなかったことだけが口惜しい。我が死後は、仏事も供養もせず堂塔も建てるな。まず鎌倉へ討伐の軍を送り、頼朝の首を斬り、我が墓の前に掛けよ。それこそが、我が望みである。」その言葉は、まことに恐ろしいものであった。もしや助かるかと、板に水を置いてその上に伏し転がったが、回復の兆しは少しもなかった。同じ四日、激しく苦しみ悶え、ついに熱のために亡くなった。
かつては馬車が行き交う音は天に響き、大地も揺るぐほどであった。天下の主、万乗の君といえどもこの栄華に勝ることはできまい。清盛はこの年、六十四歳であった。老衰というには早いが、宿命が尽きれば、神仏の威光も失われ大法・秘法の効験もなく、諸天の加護も及ばない。まして人の思いなど、どうすることもできない。身代わりとなって命を捧げようとした数万の軍勢が、堂上堂下に居並んでいても、目に見えず力にも抗えぬ「無常の殺鬼」には、一瞬たりとも立ち向かうことはできなかった。死出の山、三瀬川を越え、黄泉の中有の旅路へ、ただ一人、向かわれたのである。日ごろ積み重ねてきた悪業ばかりが、獄卒となって迎えに来たのであろうか。あわれなことであった。同じ七日、愛宕にて荼毘に付され煙となった。遺骨は円実法眼が首に掛け、摂津国へ下り、経の島に納められた。かつて日本一州に名を轟かせ、威を振るった人も、その身は一時の煙となって空に立ち上り、骨はしばし浜の真砂にまぎれ、ついには虚しい土となってしまわれた。
次のお話
▶経之嶋
ご案内
演奏会で語る平曲を現代語訳にしています。
▶平家物語現代語訳一覧
平家琵琶の伴奏で平家物語を聞いてみませんか。
▶演奏会一覧
▶平曲を聞く