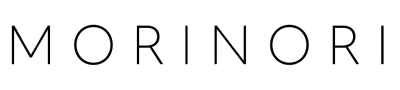【後編】平家物語『敦盛最期』現代語訳あらすじと平家琵琶の語り
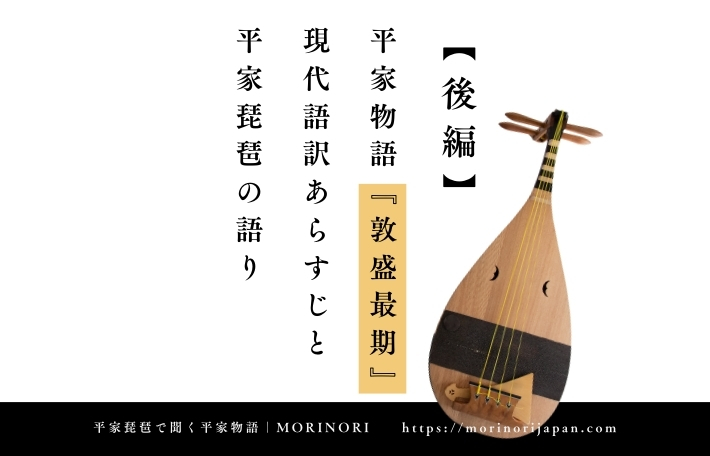
平曲の譜面『敦盛最期』から書き起こした文章を現代語訳にしています
▶前編はこちら
『敦盛最期』 場面5
※音量にご注意ください
平家物語『敦盛最期』 場面5
7:54秒
収録:2024年7月4日
原文
熊谷あまりにいとほしくて、いづくに刀を立つべしとも覚えず。目もくれ心も消へ果てて前後不覚に覚えけれども、さてしも有るべきことならねば、泣く泣く首をぞかひてんげる。あはれ、弓矢取る身ほど口惜しかりける事はなし。武芸の家に生まれずば、なにしに、ただいまかかる憂き目をば見るべきとて、袖を顔に押し当てて、さめざめとぞ泣き居たる。
現代語訳
熊谷はあまりにも哀れに思い、どこに刀を立てるべきかもわからなかった。目もくらみ、心も消え果てて前後不覚になったが、そうしてばかりはいられず、泣く泣く首をはねた。ああ、弓矢を取る身ほどつらいことはない。武芸の家に生まれなければ、どうして今こんな辛い目を見ることがあるだろうかと、袖を顔に押し当てて、静かに泣き続けた。
『敦盛最期』 場面6
※音量にご注意ください
平家物語『敦盛最期』 場面6
4:29秒
収録:2024年7月4日
原文
さてしも有るべきことならねば、首を包まんとて鎧直垂を解いて見ければ、錦の袋に入れられたる、笛をぞ腰にさされたる。あないとほし。この暁城の内にて、管絃し給ひつる人は、この人々にておわします。当時味方に東国の勢何万騎かあるらめども、軍の陣へ笛持つ者はよもあらじ。上臈はなほも優しかりけるものをとて、これを取って大将軍の御見参に入れたりければ、その座に並居たまへる人々みな、鎧の袖をぞ濡らされける。
現代語訳
そうしてばかりもいられないので、首を包もうと鎧直垂を解いてみると、錦の袋に入れられた笛が腰に挿してあった。ああ、なんと哀れなことだ。この明け方城の中で管絃をしていたのは、この人たちだったのだ。その当時、味方には東国の兵が何万騎もいたが、戦場に笛を持っている者は他にいないだろう。高貴な身分の者は本当に優雅なものだと、これを取って大将軍に見せると、その場にいた人々は皆、鎧の袖を涙で濡らした。
『敦盛最期』 場面7
※音量にご注意ください
平家物語『敦盛最期』 場面7
7:37秒
収録:2024年7月4日
原文
後にきけば、修理の大夫経盛の乙子、大夫敦盛とて生年十七にぞなられける。それよりしてこそ、熊谷が発心の心は出で来にけれ。件の笛は、祖父忠盛笛の上手にて、鳥羽の院より下し賜はられたりしを、経盛相傳せられたりけるを、敦盛笛の器量たるによって、持たれたりけるとかや。名をば小枝とこそ申しけれ。狂言綺語の理とは云いながら、終に讃仏乗の因となるこそあはれなれ。
現代語訳
後に聞けば、修理大夫経盛の次男大夫敦盛は、年齢十七歳であった。それからというもの、熊谷に出家の心が芽生えたのだった。その笛は、祖父忠盛が笛の名手で、鳥羽院から下賜されたものであり、経盛に受け継がれたものだったが、敦盛がその器量により所持していたものであった。笛の名は「小枝」と呼ばれていた。狂言綺語(言葉巧みに飾った物語・戯曲)ではあるが、終に讃仏乗(仏の功徳をたたえること)の因となったのは哀れなことであった。
ご案内
演奏会で語る平曲を現代語訳にしています。
▶平家物語現代語訳一覧
平家琵琶の伴奏で平家物語を聞いてみませんか。
▶演奏会一覧
▶平曲を聞く