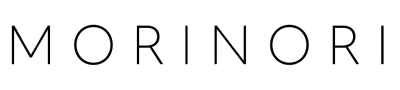平重衡|平家物語巻第十『千寿』現代語訳あらすじ

平曲|千寿(せんじゅ)

▲画面をクリックすると再生されます(音量にご注意ください)
時間|17分14秒
物語|平家物語巻第十『千寿』
詞章
十悪といへどもなほ引摂すといふ朗詠をして、極楽願はん人は皆弥陀の名号を唱ふべしといふ今様を、四五返うたひ澄ましたりければ、その時三位の中将盃を傾けらる、千寿の前賜はつて狩野の介に差す、宗茂が飲むとき琴をぞ弾澄したる、三位の中将この楽をば普通には五常楽といへども、今重衡が為には後生楽とこそ観ずべけれ、やがて往生の急を弾んと戯れ琵琶を取り、転手を捩ぢて、皇麞の急をぞ弾かれける、更行ままに万心もすみければ、あな思はずや吾妻にもかかる優なる人のありけるよ、夫れ何事にてもあれ今一声と宣へば、千寿の前重ねて一樹の陰に宿りあひ同じ流れを結ぶも、皆是前世の契りといふ白拍子を、誠に面白ふかぞへたりければ、三位の中将も燈暗ふしては数行虞氏が涙といふ朗詠をぞせられける。

平家物語巻第十『千寿』現代語訳あらすじ
※平曲の譜面『千寿』から書き起こした文章を現代語訳にしています
その後、兵衛佐殿(源頼朝)は三位中将殿(平重衡)と対面して「朝廷の敵を平らげ、父の恥をそそごうと決意した以上、平家一門の方々を滅ぼし申し上げることは覚悟の上でしたが、まさかこのように直接お目にかかることになろうとは、夢にも思っておりませんでした。この分では、いずれ屋島の大臣殿(平宗盛)ともお会いすることになるでしょう。そもそも南都(奈良)炎上の件は、亡き入道相国殿の命によるものですか、それとも貴殿のその場での判断だったのでしょうか。いずれにせよ、これほど凄まじい罪業はありません」と言った。
これに対し三位中将は「南都の炎上は入道相国の命でもなく、私の本意でもない。ただ衆徒の悪行を鎮めるために向かったところ、不運にも伽藍が滅亡するに至った。もはや人力の及ばぬ運命であった。今さら言い訳をするつもりはない。かつては源平が左右に並んで朝廷を守護していたが、近年源氏の運が尽きていたことは誰もが知るところだ。わが平家は保元・平治の乱以来、たびたび朝敵を平らげ、恩賞は身に余り、(安徳天皇の)外祖父として太政大臣にまで昇りつめた。一族の昇進者は六十余人を数え、二十余年の間栄華を極めた。それにつけても、『帝の敵を討った者は七代まで朝恩に浴する』という言葉は、全くの嘘であった。亡き相国は帝のために命を懸けたことも度々あったが、その栄華は一代限りの幸いに過ぎず、子孫がこのようになるとは思いもしなかった。運が尽き都を落ちてからは、屍を野にさらし、汚名を西海の波に流すものと覚悟していたが、こうして生きたまま捕らわれ鎌倉まで下ってきた。ただ前世の宿業が口惜しいばかりだ。しかし、かつての中国でも、殷の湯王や周の文王といった名君ですら囚われの身となった例がある。古の聖人でさえそうならば、この末世においてはなおさらのこと。弓矢取る身の習いとして、敵の手に渡って死ぬことは決して恥ではない。ただ情けとして、一刻も早く首をはねていただきたい。」そう言って、その後は何も語らなかった。
御前にいた梶原平三景時が、「あっぱれ大将軍よ」と涙を流した。これを見て大名小名も皆、袖を濡らした。兵衛佐殿もさすがに気恥ずかしさを感じたのか「平家を頼朝個人の敵とは思っていない。ただ、朝廷の命こそが重いのだ」と言って立ち去った。
三位中将は奈良で焼かれた伽藍の敵であるから、大衆がさまざまに訴えることもあろうとして、伊豆国の住人狩野介宗茂に預けられた。その有様は冥土において娑婆世界の罪人が、七日ごとに十王の手に渡されるのもこのようであろうかと思われた。狩野介は情けある者でことさらに厳しく扱うことはせず、いたわり慰め湯殿を設けて湯を引かせた。中将は道すがらの汗が不快であったので、身を清めまもなく命を失うであろうと思っていたところ、年のころ二十ばかりの女房が現れた。色白く清らかで髪のかかりも美しく、目結の帷子に染付の湯巻をして、湯殿の戸を押し開けて入ってきた。やがてまた十四五ほどの女の童が、髪は袙長に結い紺村濃の帷子を着て、楾盥に櫛を入れて持ってきた。
中将はこの女房の介添えで湯に入り、しばらく浴び髪を洗って上がった。女房が暇乞いして帰ろうとするとき「男はさほどでもないでしょうが、女にはお労しく見えます。何事でも思い残すことがあれば申し出よと、兵衛佐殿がおっしゃっていました」と伝えた。中将は「今はこのような身となって何を思うことがあろうか、ただ出家したい」と答えた。女房はその由を佐殿に申し上げたが、頼朝の私敵であればこそ朝敵として預かっているので、到底かなわぬと返された。その旨が中将に伝えられると、守護の武士に「先程の女房はいかにも優しかったが、名は何という者か」と尋ねた。武士は「あれは手越の長者の娘で、千寿の前と申します。容姿も心根もこの上なく優れているというので、この二、三年は佐殿の側に召し置かれているのです」と答えた。
その夕べ、雨が降り万物が寂しげな折に、千寿の前が琵琶と琴を(供の者に)持たせてやって来た。狩野介も情けある者で、家の子や郎等十余人を引き連れて中将の前に参上し、酒を勧めた。中将は少し口にしたものの、ひどく興ざめた様子であった。狩野介は、「頼朝殿からも、手落ちがあって私を恨むようなことがないよう、何事も望みがあれば承れと仰せつかっているのです」と伝え、重ねて酒を勧めた。千寿の前は酌をし、「羅綺の重衣たる情無き事を機婦に妬む」という朗詠を二度ほど歌い上げた。
三位中将は、「この朗詠を唱える者を、北野天神(菅原道真)が日に三度空を舞って守ろうと誓われたという。しかし、私は今生では既に見捨てられた身である。いまさら加護を受けたところで何になろう。ただ、これによって罪障が少しでも軽くなるというのであれば、その調べに従おう」と述べた。これに応じ、千寿の前はさらに「十悪といえどもなお引摂す」という朗詠を行い、続けて「極楽を願わん人は皆、弥陀の名号を唱えるべし」という今様を、四、五回ほど歌い上げた。その時、中将はようやく盃を傾け、千寿の前はその返杯を受けて狩野介に差した。宗茂が酒を飲む間、彼女は琴を弾き澄ました。
三位中将は、「この曲は世間では『五常楽』と呼ばれているが、今の私にとっては後生の楽しみである『後生楽(ごしょうらく)』と解すべきであろう。さらには(急いで極楽へ往生するという意味を込めて)『往生の急』を弾こう」と洒落を言い、琵琶を手に取って糸巻きをひねり、『皇麞の急』を弾きこなした。夜が更け、人々の心も澄み渡ったころ、重衡は「思いがけず、この東国にもこれほど優雅な人がいたものだ。何でもよいもう一声聞かせてほしい」と促した。それに応じ、千寿の前は「一樹の陰に宿りあひ同じ流れを結ぶも、皆是前世の契り」という趣旨の白拍子を歌い上げた。
三位中将もこれに応え「燈暗うしては数行虞氏が涙」という詩を朗詠した。この朗詠の背景には、かつて楚の項羽が漢の高祖と天下を争って敗れた際、愛馬の騅が進まず、后の虞氏との別れを夜通し嘆き悲しんだという故事がある。次第に暗くなる灯火の下で、心細さに涙を流した虞氏の悲哀を、捕らわれの身である己の境遇に重ねて思い出したのであろう。
夜が明けると武士たちは皆暇乞いをして退出し、千寿の前も帰途についた。折しも頼朝は持仏堂で法華経を読んでいたが、帰ってきた千寿の前を見て微笑み、「昨夜のもてなし役は、実に興味深く務め上げたものだ」と声をかけた。頼朝は重衡の奏でる琵琶の撥音や朗詠を夜通し密かに立ち聞きしており、「平家の人々は戦のことばかり考えていると思っていたが、これほどまでに優雅で優れた人物であったのか」と感嘆の意を漏らした。そばにいた斎院次官親義も、「平家は代々歌人や才人の家系であり、かつて人々を花に例えた際、三位の中将殿は牡丹の花に例えられていました」と述べた。
その後、中将が南都へ引き渡されて処刑されたと聞くと、千寿の前はそれが深い物思いの種となった。彼女は姿を変えて墨染の衣をまとい、信濃国の善光寺へ赴くと後世菩提を熱心に弔い、自身も往生の本懐を遂げたという。
前の物語
海道下
ご案内
演奏会で語る平曲を現代語訳にしています。
▶平家物語現代語訳一覧
平家琵琶の伴奏で平家物語を聞いてみませんか。
▶演奏会一覧
▶平曲を聞く