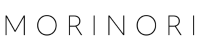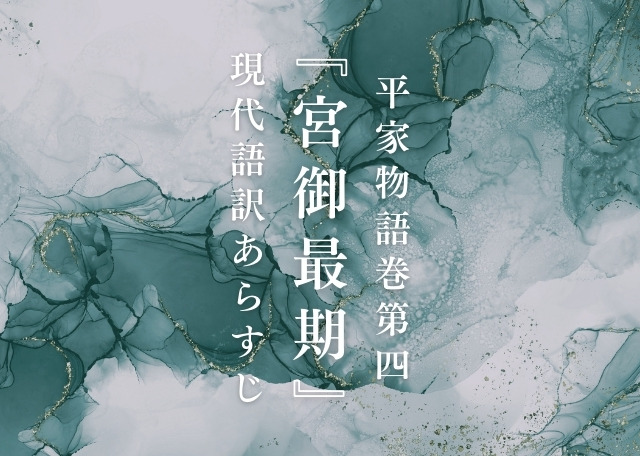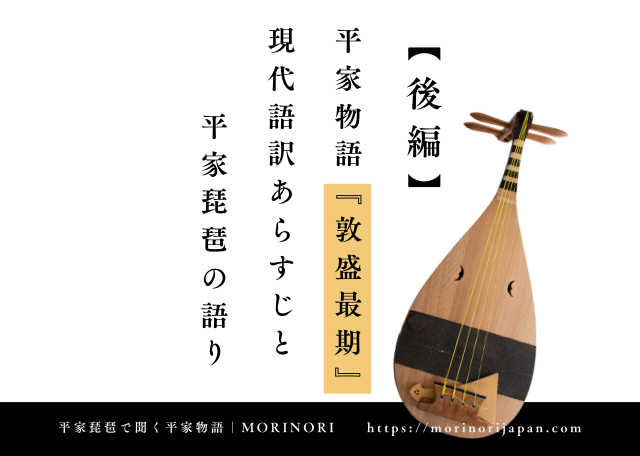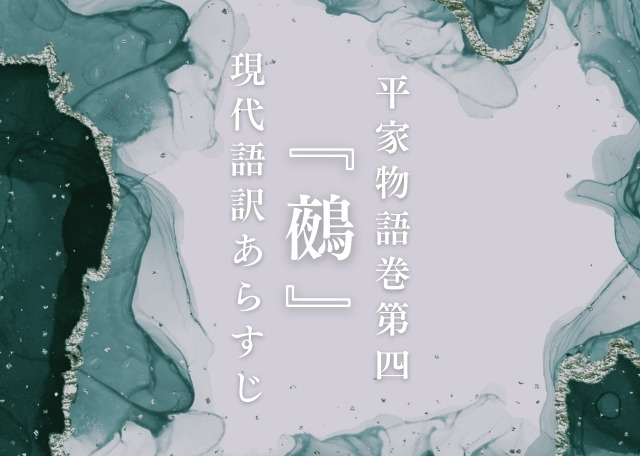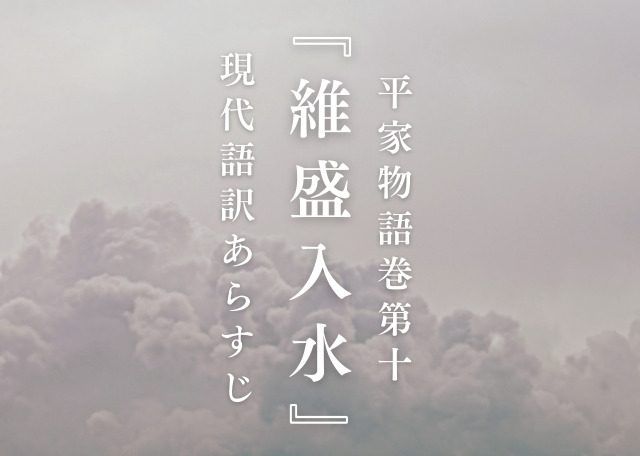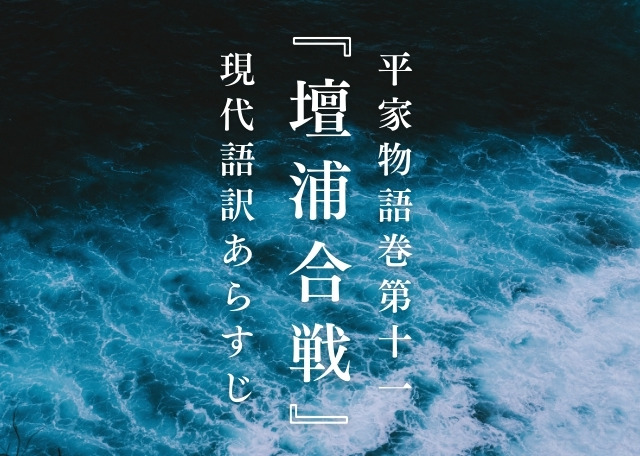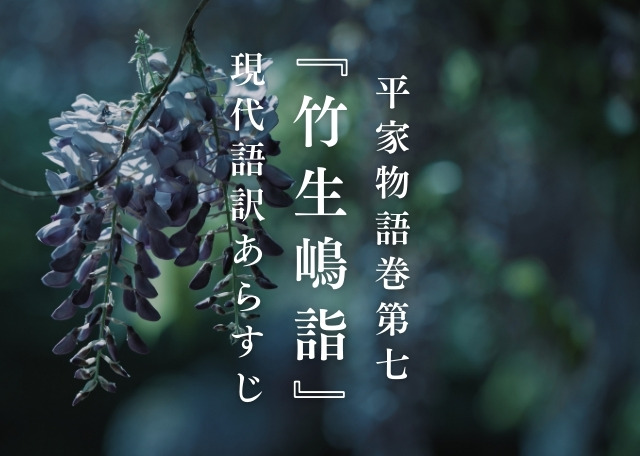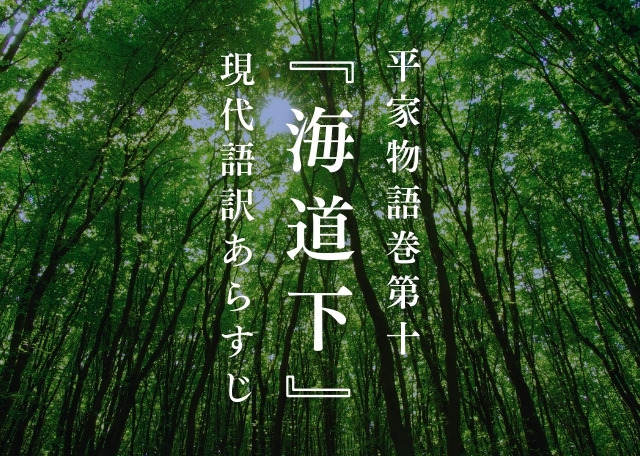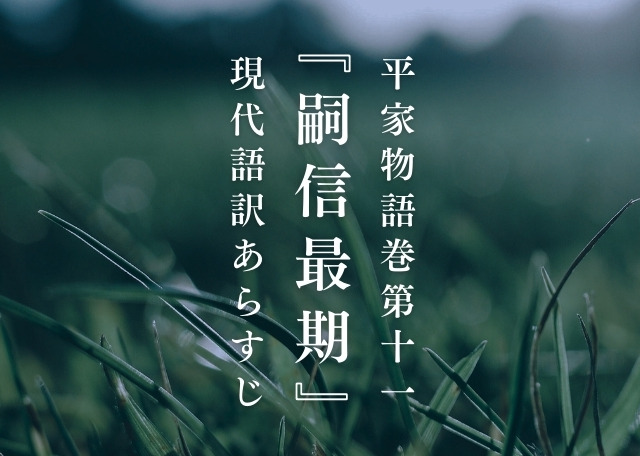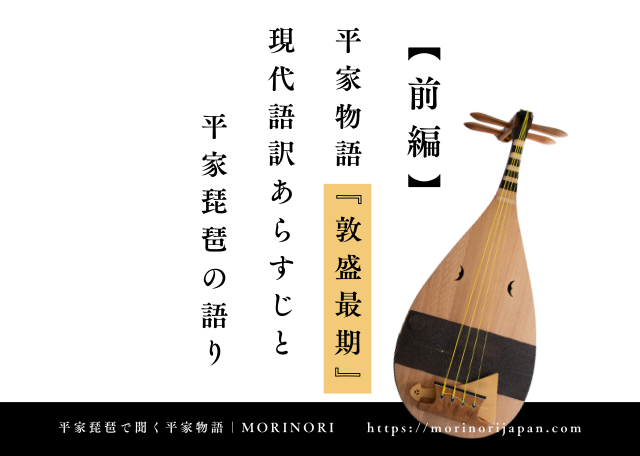ようこそお越しくださいました。
ここは、平曲(平家琵琶の伴奏で平家物語を語るもの)の小さな演奏会や講座を行っている盛典のサイトです。このページでは平家物語巻第四『橋合戦(はしがっせん)』の現代語訳あらすじを紹介しています。
▼初めての方へ
https://morinorijapan.com/welcome
▼平曲を聞く
https://morinorijapan.com/tale-of-the-heike-sound-archive
▼平家物語現代語訳一覧はこちら
演奏会や講座等で行う平家物語を現代語訳にしています
https://morinorijapan.com/category/tale-of-the-heike/
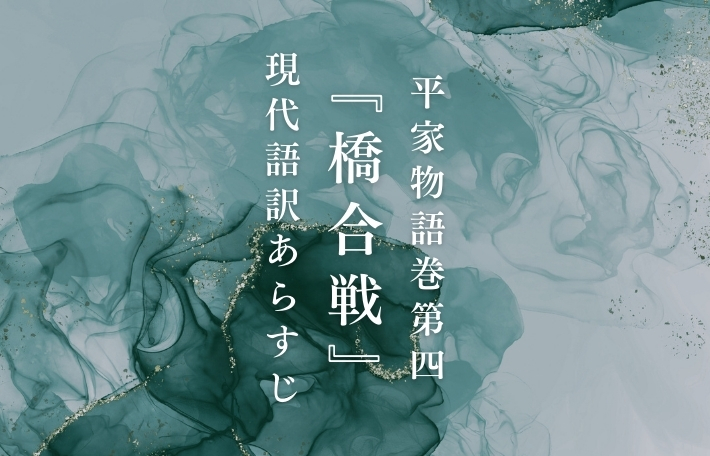
平家物語巻第四『橋合戦』簡単なあらすじ
以仁王(高倉宮)は平等院へ落ち延びるも、疲労で六度も落馬。平家は総勢二万八千余騎で宇治橋へ迫り、橋が外されていたために先陣が多数水に沈む。両軍が激突する中、五智院但馬や筒井の浄妙坊が奮闘する。平家方は増水した宇治川を前に進退を協議するが、十七歳の足利又太郎忠綱が名乗りを上げ、勇敢に川へ打ち入る。続く三百余騎とともに、見事に渡河し、戦線を押し上げた。
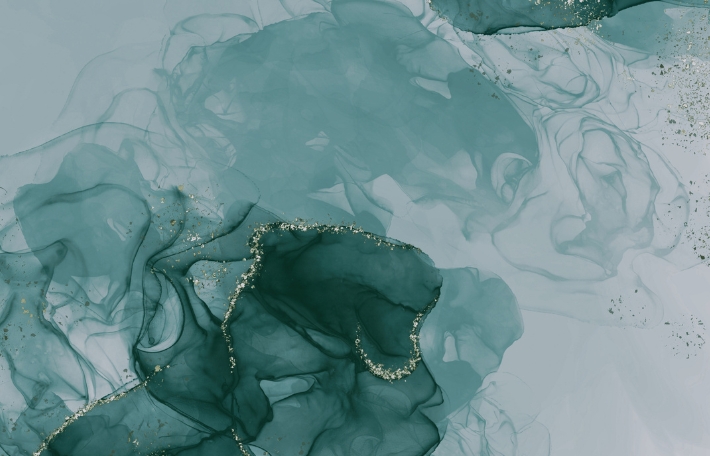
平家物語巻第四『橋合戦』現代語訳全文
※平曲の譜面『橋合戦』から書き起こした文章を現代語訳にしています
そうしているうちに、宮(以仁王・高倉宮)は宇治と平等院の間で六度も落馬された。これは、前夜に一睡もなさらなかったためであろうとされた。そこで、宇治橋の三間を引き外し、平等院へお入りになり、しばらくの間ご休息なさった。六波羅では、「宮が南都へお逃げになったようだ。すぐに追いかけて討ち取れ」との命が下され、大将軍には左兵衛督平知盛、頭中将平重衡、薩摩守平忠度が任じられた。侍大将には上総守忠清とその子である上総太郎判官忠綱、飛騨守景家とその子の飛騨太郎判官景高、河内判官秀国、高橋判官長綱、武蔵三郎左衛門有国、越中次郎兵衛尉盛嗣、上総五郎兵衛忠光、悪七兵衛景清らがあたった。このようにして、総勢二万八千余騎の軍勢が木幡山を越え、宇治橋のたもとへと押し寄せた。
平等院に宮がいると見定めて鬨の声を三度上げると、宮方でもこれに呼応して鬨の声を上げた。先陣の兵たちは「橋が引いてあるぞ、油断をするな」と声を上げていたが、後方の兵たちはその声を聞かず我先にと突き進んだため、先陣のうち二百余騎が橋の切れた箇所から落ち、水に沈んで命を落とした。そのような中、両軍は橋の両端に陣取り、矢を射交わした。宮方からは大矢俊長、五智院但馬、渡辺省、渡辺授、続源太らが射た矢が、敵の楯を貫き、鎧すらも通して突き刺さった。
源三位入道頼政は、今日が最期になるだろうと覚悟していたのか、長絹の直垂の上に科革威の鎧を着け、あえて甲はかぶらなかった。嫡子の伊豆守仲綱も、赤地の錦の直垂に黒糸威の鎧を着け、弓を強く引くために、やはり甲は身につけていなかった。
ここに、五智院但馬が大長刀の鞘を外し、ただ一人、橋の上へと進み出た。平家方はこれを見て、「射取れ、射取れ」と声を上げ、弓を差し詰め引き詰めして、散々に矢を射かけたが、但馬はまったく動じることなく、上から飛んでくる矢は突いてくぐり、下から来る矢は飛び越え、前に進んでくる敵を長刀で次々に斬り倒した。敵味方を問わず目を奪われ、以後「矢切の但馬」と呼ばれるようになった。
また、堂衆の中に筒井の浄妙明秀という者がいた。褐色の直垂に黒革威の鎧を着て、五枚甲の緒を締め、黒漆の太刀を帯び、二十四本の黒保呂の矢を背負い、塗籠籐の弓に、好んで持つ白柄の大長刀を添えて、やはりただ一人、橋の上へと進み出た。そして大音声を上げて「遠くにいる者はその名を聞け、近くにいる者はこの姿を見よ。三井寺には隠れもない。堂衆の中に筒井浄妙明秀という一人で千人に当たる兵がいる。我こそはと思う者たちは来るがいい、相手をしてやろう。」そう言いながら、背負っていた二十四本の矢を差し詰め引き詰め、激しく矢を放った。
矢を次々に放ち、敵十一人を射殺し、十二人に重傷を負わせた。箙には一本の矢だけが残った。その後、弓をからっと投げ捨て、箙も解いて捨てた。つらぬきを脱ぎ捨てて裸足となり、橋の横板の上をさらさらと駆け抜けていった。人々は恐れて橋を渡れなかったが、浄妙坊にとっては一条や二条の大路を歩いているかのような振る舞いであった。長刀を手に、向かってくる敵五人を薙ぎ倒し、さらに六人目の敵に出くわしたとき、長刀が中ほどから折れてしまったため、そのまま捨てた。
その後、太刀を抜いて斬りまわる中で、蜘蛛手、角縄、十文字、蜻蜒返り、水車、八方と、あらゆる型を織り交ぜて敵を斬った。向かってくる敵八人を斬り伏せ、九人目の敵に太刀を振り下ろしたところ、甲の鉢にあまりにも強く当てたため、目貫のあたりからちょうと折れ、太刀はくつりと抜けて川へさぶと落ちてしまった。頼みとするものは、ただ腰の短刀のみ。死ぬ覚悟で、狂ったように戦い続けた。
浄妙坊は多くの傷を負い、這うようにしてなんとか引き返そうとしていた。そのとき、乗円房阿闍梨慶秀に仕えていた、一来法師という大力で剛勇な僧兵が、浄妙坊のすぐ後ろについて戦っていた。しかし橋の行桁は狭く、並んで通ることなどできなかったため、一来法師は浄妙坊の兜の手先に手をかけて「失礼します、浄妙坊」と声をかけ、彼の肩を踏み台にして、ぐんと跳び越えて前に出て戦った。そして、一来法師はそのまま討死したのであった。
浄妙坊は這うようにして平等院の門前の芝生まで戻り、そこで鎧や武具を脱いで置いた。自らの鎧に突き刺さった矢の数を数えてみると、六十三本、裏を掻いて刺さった矢も五本あった。
しかし、どれも致命傷には至らず、大きな怪我ではなかったため、傷ついたところに灸をすえて治療を施し、頭に布を巻いて髪をまとめ、浄衣を着て、折れた弓を杖代わりにしながら、平足駄を履いて「南無阿弥陀仏」と唱えつつ、奈良の方へと去っていった。
その後は、浄妙坊が橋を渡った姿を手本として、源三位入道頼政の一族である渡辺党や三井寺の僧兵たちが、我先にと次々に橋の行桁を駆けて渡っていった。中には、戦利品を奪い取って引き返す者もいれば、敵と組み合って刺し違えたまま川へ飛び込む者もいた。橋の上での激しい戦いはまるで炎が上がっているかのように見えた。
平家方の侍大将上総守忠清が大将軍の御前に進み出て「ご覧くださいませ。橋の上での戦は、手痛く苦戦しております。今は無理に橋を渡ろうとせず、川を渡るべきかと存じます。されど、折からの五月雨で川は増水しており、もし渡ろうとすれば人馬ともに多くが溺れて失われることでしょう。いっそ淀の渡し口から回るべきか、または河内方面へまわるべきか、それとも水が引くのを待つべきか――どうかご判断を」
それに対し、下野国の住人である足利又太郎忠綱、当年十七歳の若武者が進み出て「淀からまわるにせよ、河内路に向かうにせよ、天竺や震旦の武者でもお呼びになって向かわせるおつもりですか、私どもにお任せください。目の前にいる敵を討たぬまま、もし宮を南都に逃してしまえば、吉野・十津川の軍勢が集まり、ますます事態は重大になるでしょう。武蔵と上野の境には利根川という大河がございます。秩父と足利が不和でたびたび合戦をしていたのですが、前面からは足利が長井の渡し、後面からは秩父が故我杉の渡しを使って攻め寄せたものです。その際、上野国の新田入道が足利に味方して用意した舟が、秩父側に打ち壊されてしまったとき『いま渡さねば、味方の恥だ』と覚悟を決め、馬筏を組んで渡ったものです。坂東武者の習いとして、敵を目の前にしながら、川を挟んだ戦に臆するなどありえません。この宇治川の深さも早さも、利根川と比べてそう違うとは思えません。さあ、諸将続け 」そう言い終わるや否や、忠綱は先陣を切って、真っ先に川へと打ち入った。
それに続いて川を渡った者たちは、大胡・大室・深須・山上・那波太郎・佐貫広綱・四郎大夫・小野寺前司太郎・辺屋子四郎らであった。郎等には、宇夫方次郎・桐生六郎・田中宗太をはじめとし、総勢三百余騎がこれに続いた。
足利又太郎忠綱は大音声を上げて「弱い馬は川下に立て、強い馬は川上に置け。馬の脚が届く間は手綱を緩めて歩ませよ。もし馬が弾んで水に浮いたら、操って泳がせよ。退こうとする者には弓の弭を取らせて引き連れよ。手と手を取り、肩を並べて渡れ。馬の頭が沈めば引き上げよ。ただし強く引きすぎて、引きかぶせるな。鞍の壺にしっかりと乗って鐙を力強く踏め。水を踏みしめたら三頭の馬の背をまとめて踏み越えよ。馬にはやさしく、水には果敢に挑め。川の中では弓を引くな。敵を見かけても矢の応酬は避けよ。常に錣を傾け、しっかり傾けて天辺を射させるな。中ほどで押し返されて落とされるな。水に抗いながら進み、必ず渡りきれ。」こうして足利の三百余騎は、一騎も流されることなく、一度にどっと宇治川の対岸へ打ち上がった。
→次のお話『宮御最期』はこちら
https://morinorijapan.com/tale-of-the-heike/miyagosaigo
→前のお話『競』はこちら
https://morinorijapan.com/tale-of-the-heike/kiou
▼平家物語現代語訳一覧はこちら
※演奏会や講座等で行う平家物語を現代語訳にしています
https://morinorijapan.com/category/tale-of-the-heike/
ここまでご覧いただきありがとうございました。
いつかどこかでお会いできますように。