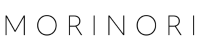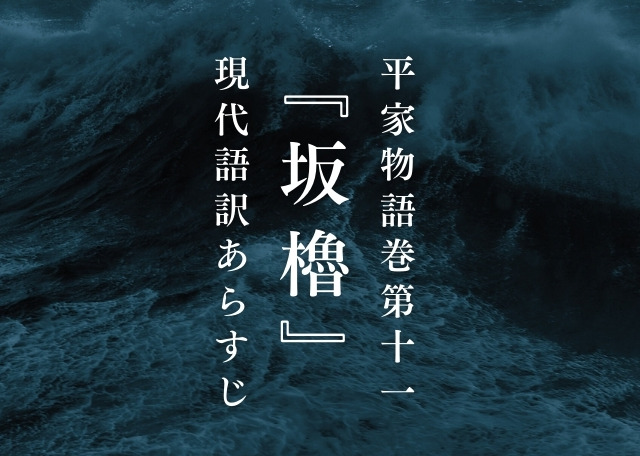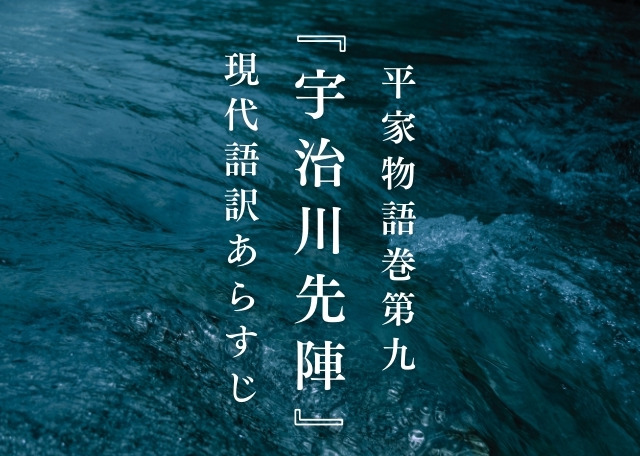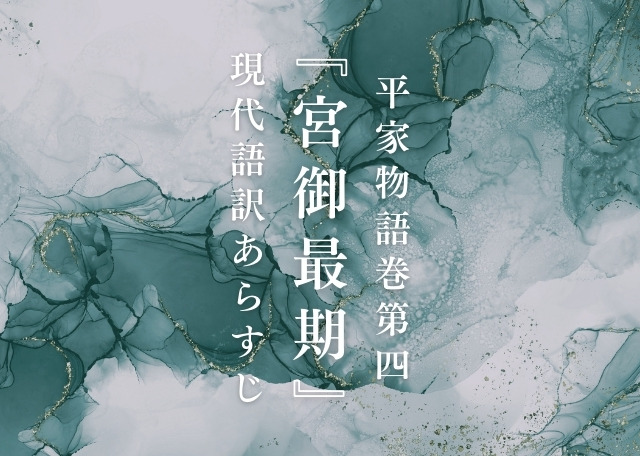ようこそお越しくださいました。
ここは、平曲(平家琵琶の伴奏で平家物語を語るもの)の小さな演奏会や講座を行っている盛典のサイトです。このページでは平家物語巻第十一『嗣信最期(つぎのぶさいご)』の現代語訳あらすじを紹介しています。拙いものですがよろしければご覧ください。
▼初めての方へ
https://morinorijapan.com/welcome
▼演目紹介
https://morinorijapan.com/performance-lineup
▼平曲を聞く
https://morinorijapan.com/tale-of-the-heike-sound-archive
▼平家物語現代語訳一覧はこちら
演奏会や講座等で行う平家物語を現代語訳にしています
https://morinorijapan.com/category/tale-of-the-heike/

平家物語巻第十一『嗣信最期』簡単なあらすじ
義経は赤地の錦の直垂と紫裾濃の鎧を身にまとい、堂々と名乗りを上げて軍場に立つ。彼に続いて一騎当千の武士たちが声を上げ勇ましく軍に参加する。平家側もこれに応じ、矢を次々に放つが、源氏の兵たちは果敢に戦い続けた。
奥州の佐藤三郎兵衛嗣信が能登殿に矢を射られ落馬し、菊王丸がその首を取ろうとするが、弟の忠信が兄を救うために矢を放ち、菊王丸を射倒す。能登殿は菊王丸を船に投げ入れるが、彼は息を引き取る。能登殿は悲しみ、戦意を失う。
嗣信は命が尽きる直前、義経と最後の言葉を交わし、自分の死を悔いず、ただ義経の未来を見届けられないことが心残りだと語る。義経は嗣信の死を哀れみ、僧を呼び寄せて弔いを頼んだ。忠信をはじめとする家臣たちは、この戦いで義経のために命を惜しまない覚悟を示した。

平家物語巻第十一『嗣信最期』現代語訳全文
※平曲の譜面『嗣信最期』から書き起こした文章を現代語訳にしています
判官(義経)はその日の装束として、赤地の錦の直垂に紫裾濃の鎧を着込み、鍬形が打たれた兜の緒を締め、金作りの太刀を腰に帯びた。二十四本の切斑の矢を背負い滋籐の弓を携えて、黒く逞しい馬に金覆輪の鞍を置いて乗り、沖の方を睨んで鐙を踏ん張って立ち上がり、大音声を上げて「一院の御使である検非違使の五位尉、源義経である」と高らかに名乗った。
続いて名乗りを上げたのは、伊豆国の住人田代の冠者信綱、武蔵国の住人金子十郎家忠、同じく与市親範、伊勢の三郎義盛であった。その後に名乗りを上げたのは、後藤兵衛実基とその息子の新兵衛基清、奥州の佐藤三郎兵衛嗣信、同じく四郎兵衛忠信、江田源三、熊井太郎、そして武蔵坊弁慶といった、一騎当千の強者たちであった。彼らは声を揃えて名乗りを上げながら、勇ましく馳せ参じた。
平家の方ではこれを見て、「ただ射取れ、射取れ」と声を上げ、ある舟は遠くから矢を放ち、またある舟は差し迫って矢を射かけた。彼らは矢を差し詰め引き詰め、次々に源氏の兵に向かって激しく矢を放ったが、源氏の兵たちはこれをものともせず、左手に弓を構えては射ち、右手に弓を持ち替えては射った。彼らは揚げ置かれた舟の陰を馬の休息場所として、勇敢に攻め戦った。
後藤兵衛実基は古参の兵であったため、磯の戦いには加わらず、まず内裏に乱入し、手当たり次第に火を放って内裏を片時のうちに焼き払った。これを聞いた大臣殿(平宗盛)が侍たちを呼び寄せ、「源氏の軍勢はどれほどの数か」と尋ねたところ、「七、八十騎には過ぎないでしょう」と答えた。これを聞いた大臣殿は、「なんと心憂いことだ。一筋ずつ髪を抜いて数えても足りないくらいの兵力であるにもかかわらず、取り囲んで討ちもせず慌てて船に乗り、内裏を焼かせてしまったのは実に悔しい」と嘆いた。
「能登殿はおらぬのか。陸に上がって一戦交えてくれ」と声を上げると、これに応じて越中の次郎兵衛盛嗣、上総五郎兵衛忠光、悪七兵衛景清を先頭に、二百余艘の兵船が漕ぎ寄せ、焼き払われた総門の前の渚に陣を取った。判官も七八十騎を率いて対峙した。
すると平家の側から、越中次郎兵衛盛嗣が船の屋形に進み出て、大音声で叫んだ。「以前、名乗りを聞いたが、海を隔てて仮名も実名もよくわからない。今日の源氏の大将軍は誰だ、名乗りを上げよ」これを受けて、伊勢の三郎義盛が進み出て「馬鹿なことを。言うまでもないが清和天皇の十代目の子孫であり、鎌倉殿の弟、九郎判官義経殿であられるぞ」盛嗣はこれを聞き、「ああそうか。かつて平治の乱で父親が討たれ、孤児となり、鞍馬寺の子として過ごし、後には商人の手伝いとして食糧を背負い、奥州まで落ち延びてさまよっていたあの小冠者のことか」と言った。
義盛はこれを聞いて、「君主のことを舌先で軽々しく言うな。お前たちこそ、北国の砥浪山の戦で打ち負け、辛うじて命を繋いで北陸道を彷徨い、乞食同然でここまで辿り着いたのだろう」と言い返した。これを聞いた盛嗣は、「何が君主の恩に満ち足りていないからといって乞食をするものか。むしろお前たちこそ、伊勢国の鈴鹿山で山賊のような真似をして生き延びていたと聞くぞ」と返した。
すると金子十郎がこれを聞き、「くだらない悪口の応酬を。自分も他人も嘘を並べて悪口を言って、誰が得をするというのだ。だが、去年の春、摂津国の一の谷で武蔵や相模の若い武士たちの手並みを見ておけば、そんな虚言を吐かずに済んだものを」と言うと弟の与市が十二束二伏の矢を引き絞ってひゅつと放った。次郎兵衛盛嗣の鎧の胸板を貫くほどに突き刺さり、ここで互いの口論は終わった。
能登殿は、舟軍にはやり方があると、鎧直垂は着ずに、唐巻染の小袖に唐綾威の鎧をまとい、厳しい作りの太刀を帯び、二十四本の矢を背負い、滋籐の弓を持って出陣した。彼は王城一の強弓の名手であり、能登殿の矢先に立つ者は、誰もその矢を避けることができなかった。特に、源氏の大将軍である源九郎義経を一矢で仕留めようと狙っていたが、源氏の軍勢もそれに気づいており、奥州の佐藤三郎兵衛嗣信、四郎兵衛忠信、江田源三、熊井太郎、そして武蔵坊弁慶といった一騎当千の猛者たちが、馬の頭を一列に並べ、大将軍の前に盾のように立ちはだかったため、能登殿は思うように攻撃できなかった。
能登殿は「その場を退け、雑兵ども」と叫びながら、矢を次々に放ち、立て続けに敵を射落としていった。瞬く間に、鎧をまとった武者たち十騎ほどが矢に貫かれて倒れた。真っ先に進んでいた奥州の佐藤三郎兵衛嗣信は、弓手の肩から馬手の脇にかけて矢で射抜かれ、耐えきれず馬から逆さまに落ちた。
そのとき能登殿に仕える童である菊王丸という大力の猛者が、嗣信の首を取ろうと飛びかかった。菊王丸は萌黄色の腹巻を着け、三枚甲の緒を締め、太刀を抜き放ち、嗣信の首を狙った。しかし、それを見た弟の佐藤四郎兵衛忠信が、兄の首を取らせまいと十三束三伏の矢を放ち、菊王丸の草摺を貫いて四つんばいに射倒した。
能登殿はこれを見て、敵に首を取らせまいと急ぎ船から飛び降り、左手に弓を持ちながら、右手で菊王丸の体を掴んで船へ投げ入れた。菊王丸は深手を負っており、これが命取りとなった。この菊王丸という童は、もともと越前三位通盛卿に仕えていたが、通盛が討たれた後は弟の能登殿に仕えるようになった。まだ十八歳の若者であった。能登殿は、この菊王丸が討たれたことをあまりにも哀れに思い、その後は合戦をしなかった。
判官も、佐藤三郎兵衛嗣信を陣の後ろに運び入れさせ、急いで馬から降りて嗣信の手を取り、「どうだ、三郎兵衛」と問いかけた。嗣信は息も絶え絶えに、「今はもうこれまでかと感じております」と答えた。義経が「思い残すことはないか」と尋ねると、嗣信は「別に思い残すことはございません。ただ一つ、君(義経)の御代を見届けることなく死ぬのが心残りです。それ以外、弓矢を取る身としては、敵の矢に当たって死ぬ覚悟は常にしておりました。とりわけ、奥州の佐藤三郎兵衛嗣信という者が源平の合戦の最中に讃岐国八島の磯で、主君の命に代わって討たれたと後世に語られ、末代までの物語になることは今生の名誉であり、冥土への思い出としてこれ以上のものはありません」と言いながら、徐々に力を失っていった。
判官は哀れに感じ、鎧の袖を涙で濡らされた。しばらくしてから、「この近くに尊い僧はいないか」と尋ね、僧を探し出し、「この者が今まさに命を落とそうとしている。どうか一日経を唱えて弔ってほしい」と頼んだ。そして、黒く太く逞しい馬に良い鞍を置き、その僧に贈った。この馬は、義経が五位の尉に任じられた際に、同じく五位に昇格させられ、「大夫黒」と呼ばれた名馬であった。一谷の合戦で、後ろの鵯越をこの馬に乗って駆け下りたことでも知られている。
嗣信の弟、忠信をはじめとする義経の家臣たちはこの様子を見て、この君のために命を失うことは、露塵ほども惜しくはないと言った。
▼続きのお話『那須与一』はこちら
https://morinorijapan.com/tale-of-the-heike/nasunoyoichi
▼平家物語現代語訳一覧はこちら
※演奏会や講座等で行う平家物語を現代語訳にしています
https://morinorijapan.com/category/tale-of-the-heike/
ここまでご覧いただきありがとうございました。
いつかどこかでお会いできますように。