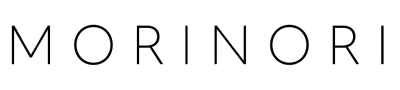以仁王|平家物語巻第四『宮御最期』現代語訳あらすじ
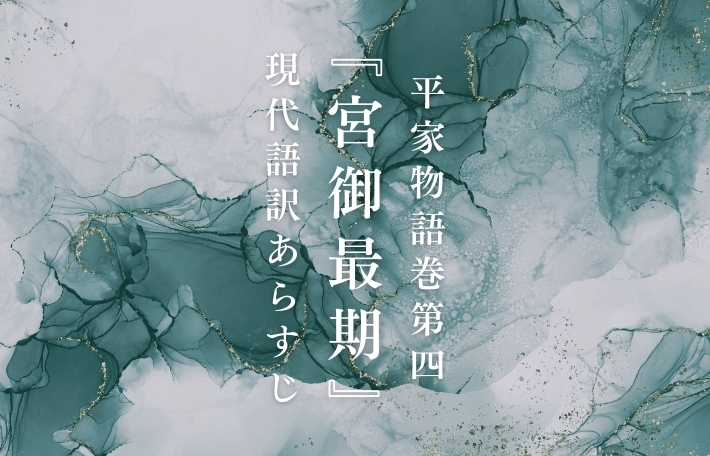
『宮御最期』簡単なあらすじ
十七歳の足利又太郎忠綱は、宇治川を果敢に渡って敵陣に攻め入る。これを受けて平家方も総勢二万八千余騎が川を渡り始め、兵たちは押し流されながらも一斉に上陸。激戦の中、宮(以仁王)は南都(奈良)へ逃れ、宇治橋で防戦していた頼政の一族・渡辺党・三井寺の僧兵たちは奮闘する。頼政の次男兼綱は敵の矢を受け討ち死に。嫡男仲綱も負傷して平等院で自害。頼政も深手を負い辞世の歌を詠んで自ら命を絶った。宮はわずか三十騎で南都へ落ち延びようとするも、平家の追撃を受け、光明山の鳥居前で矢を受けて落馬、首を取られる。南都の僧兵七千余人は迎えに向かうも、わずかの差で間に合わなかった。

平家物語巻第四『宮御最期』現代語訳あらすじ
※平曲の譜面『宮御最期』から書き起こした文章を現代語訳にしています
足利又太郎忠綱のその日の装束は、朽葉色の綾織の直垂に、赤糸威しの鎧を着込み、高角を打った甲の緒を締め、金装飾の太刀を腰に帯び、二十四本の斑模様の鏃の矢を負い、重籐の弓を手にしていた。連銭模様の葦毛の馬に、柏木の縁取りに木菟を打った金の覆輪の鞍を据えていた。
鐙に力を込めて立ち上がると、大音声をあげて「かつて朝敵・平将門を討ち、後世に名を残した俵藤太秀郷の十代の子孫、足利太郎俊綱の子、又太郎忠綱、年十七にしてここに参上仕る。無官無位の身にて宮に矢を向け弓を引くことは、天に対して恐れ多きことではありますが、弓矢の冥加も、すべては平家の御身にこそ留まることでしょう。三位入道殿の御方において、我こそはと思う者あらば、寄って参られよ、見参仕る。」そう言い放つや、平等院の門の内へ攻め入り戦いを挑んだ。
大将軍左兵衛督の知盛はこれを見て、「浅いぞ、渡れ渡れ」と命じた。すると、二万八千余騎の兵たちは一斉に川に打ち入って渡り始めた。あれほど流れの速い宇治川であったが、馬や人が一斉に川に入り、流れをせき止めるような勢いで、水は逆に上流へと湛えられるほどであった。雑兵たちは馬の腹の下に取り付き、取り付きして渡るうちに、膝より上を濡らさずに渡りきる者も多かった。一方で、馬から外れたり、流れに巻き込まれた者たちはひとたまりもなく、水にのまれて流された。この時、伊賀・伊勢両国から参陣していた官兵たちは、馬筏が押し破られてしまい、六百余騎が宇治川の濁流に流されたのだった。
萌黄色、緋色威、赤色威、さまざまな色の鎧を身にまとった兵たちが、川面に浮いたり沈んだり、揺れ動くさまは、まるで神南備山の紅葉が峰の風に吹かれて、立田川の秋の夕暮れ、井堰に引っかかって流れきれずにたなびいているようなありさまだった。
その中で、緋色の鎧を着た三人の武者が、網代にかかって浮いたり沈んだりしているのを、伊豆守(源仲綱)が見て、次のように詠んだ。
伊勢武者はみな緋縅の鎧着て 宇治の網代にかかりぬるかな(伊勢の武者たちは皆緋威しの鎧を着て、宇治川の網代に掛かってしまったようだ)
黒田後平四郎、日野十郎、乙部弥七という者たちは、いずれも伊勢国の住人であった。中でも日野十郎は古参の武士であったため、弓の弭を岩の隙間に捩じ込んで立て、それを頼りに川岸をよじ登り、自らの手で残る二人も引き上げて助け出したという。
やがて大勢の軍勢がみな川を渡り終えると、平等院の門の内へと攻め入り、幾度も攻撃をしかけ、激しく戦った。その混乱のさなかに、宮は先に南都へとお逃れになり、三位入道頼政の一族、渡辺党、三井寺の大衆らはあとに残って、敵の進軍を防ぎながら必死に矢を射かけて応戦した。
源三位入道頼政は、七十歳を過ぎてなお出陣し戦っていたが、戦の中で左膝の辺りを激しく射抜かれた。重い傷であったため、もはやこれまでと悟り、静かに自害しようと平等院の門の内へと退こうとした。その時、敵が襲いかかってきたため、次男の源大夫判官兼綱(紺地の錦の直垂に唐綾威の鎧をまとい、連銭葦毛の馬に金の覆輪の鞍を置いて乗っていた)が、父を助けようと立ち返っては敵を防ぎ、応戦した。
平家方の侍大将上総太郎判官が放った矢が、源大夫判官兼綱の甲の内側に命中し、兼綱は怯んでしまった。そこへ、上総守の従者である次郎丸という大力無双の武者(萌黄匂の腹巻を着け、三枚甲の緒を締めていた)が兼綱に並びかかり、力任せに組みついた。しかし、兼綱もまた並外れた力を持つ者であったため、次郎丸を押さえつけ、首を取ろうとした。ところが、そこへ平家方の侍たち十四、五騎が次々と押し寄せ、折り重なって攻めかかり、ついに兼綱はその場で討たれてしまった。
嫡子伊豆守仲綱もまた奮戦し、多くの傷を負って、ついに平等院の釣殿にて自害した。その首は、下河辺藤三郎清親によって取られ、大床の下へ投げ入れられた。六条蔵人仲家と、その嫡子蔵人太郎仲光も激しく戦い、多くの敵を討ち取りながら、父子ともども同じ場所で討死した。この仲家という人物は、かつて故帯刀先生義方の嫡子であった。父が討たれた後は、三位入道の養子となり、頼政が不憫に思って日頃から深い誓いを交わしていた。その約束を違えることなく、一所で命を絶ったというのは、まことに哀れであった。
源三位入道頼政は、家来の渡辺長七唱を呼び寄せ、「私の首を討て」と命じた。しかし、主君の首を自らの手で討つことのあまりの悲しさに、長七唱は「それは仕りかねます。御自害なされましたなら、給わりましょう」と申し上げた。頼政はそれを聞いて西に向かって手を合わせ、声高らかに十念唱えた後、最後の歌を詠まれた。
埋木の 花咲くことも なかりしに 実のなる果てぞ かなしき(人知れず埋もれていた木は、花を咲かせることもなかった。実を結んだと思った矢先に果てるとは悲しいことだ。)
この歌を最期の詞として、太刀の先を腹に突き立て、うつぶしたまま貫いて命を絶たれた。最期にあっても、若い頃から傾倒していた和歌の道を忘れなかった。その首は長七唱が受け取り、敵の目を避けながら紛れて脱出し、石とともに括って宇治川の深いところへ沈めたという。
平家の武士たちは、何としても渡辺党の競滝口を生け捕りにしようと狙っていたが、競もすでにそれを察しており、奮戦の末、宇治川に飛び込んで自ら腹を掻き切って果てたのであった。
円満院大輔源覚は、右手に大太刀、左手に大長刀を携えたまま、敵の真っただ中を割って進み、宇治川へと飛び込んだ。甲冑や武具を一つも脱ぎ捨てず、そのまま水中を潜って対岸まで泳ぎ着いた。そして岸に上がり、少し高い場所まで駆け登ると、大声で「どうした、平家の公達たちよ。こちらへ来るのは大変なようだな!」と言い放つと、そのまま三井寺へと戻っていった。
平家の侍大将飛騨守景家は、古くからの歴戦の兵であったため、「この戦の混乱に乗じて、宮はきっと南都へ落ち延びられるだろう」と推し量り、混甲の兵四、五百騎を率いて、鞭と鐙を揃えて全速力で追撃した。
案の定、宮はわずか三十騎ほどの供を連れて落ち延びるところであった。追っ手は、光明山の鳥居の前でこれに追いつき、雨のように矢を射かけた。その中のどの矢かは分からなかったが、一本が宮の左の脇腹に突き刺さり、宮は馬から落ちて、ついに首を取られてしまわれた。その場にお供していた鬼佐渡、荒土佐、伊賀の君、荒大夫俊秀(らも、「命など惜しむ理由はない」と、命懸けで奮戦し、主君と同じ場所で討ち死にした。
乳母子の六条亮大夫宗信は、馬が弱って動けず、敵は次々と押し寄せてきていたため、とても逃げ切れる状況ではなかった。そこで、新野池へ飛び込んで水面の浮草を顔にかぶせ、身を震わせながらじっとしていた。敵は彼のすぐ前をそのまま通り過ぎていった。
しばらくして、敵の四、五百騎ほどが騒がしく通っていく中で、蔀の下にかき出された、浄衣を着た首のない遺体が目に入った。それを見ると、まさにそれは宮であった。かつて宮が「私が死んだら、棺にこの笛を入れてくれ」とおっしゃった、小枝と呼ばれる御笛も、まだその腰に差されたままであった。宗信は走り出て遺体に取りすがりたいと思ったが、恐ろしさにかられて、それすら叶えることができなかった。
敵がすべて通り過ぎた後、六条亮大夫宗信は池から這い上がり、濡れた衣類を絞って身に着け、泣く泣く都へ戻っていった。それを見て、彼を憎まないものはいなかった。
一方その頃、南都の僧兵七千余人は、甲冑の緒を締めて宮を迎えに向かっていた。先陣はすでに木津まで進んでいたが、後陣はまだ興福寺の南大門のあたりに揺らいでいた。そのさなか、「宮はすでに光明山の鳥居の前で討たれた」との報せが届いた。
大衆(僧兵たち)は、力及ばず、ただ涙を押し殺してそこに留まるしかなかった。あと五十町ほどの距離で合流できたが、それを待たずして討たれてしまった宮の運命は、まことに哀れであった。
次の物語
▶鵺
ご案内
演奏会で語る平曲を現代語訳にしています。
▶平家物語現代語訳一覧
平家琵琶の伴奏で平家物語を聞いてみませんか。
▶演奏会一覧
▶平曲を聞く