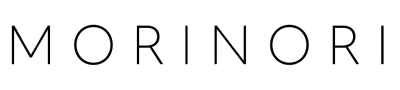BLOG
記事
-
 KAJIWARA25|インスタレーションノートを公開しました
KAJIWARA25|インスタレーションノートを公開しました -
 平曲「生食」「宇治川」「二度魁」演奏動画を公開しました
平曲「生食」「宇治川」「二度魁」演奏動画を公開しました -
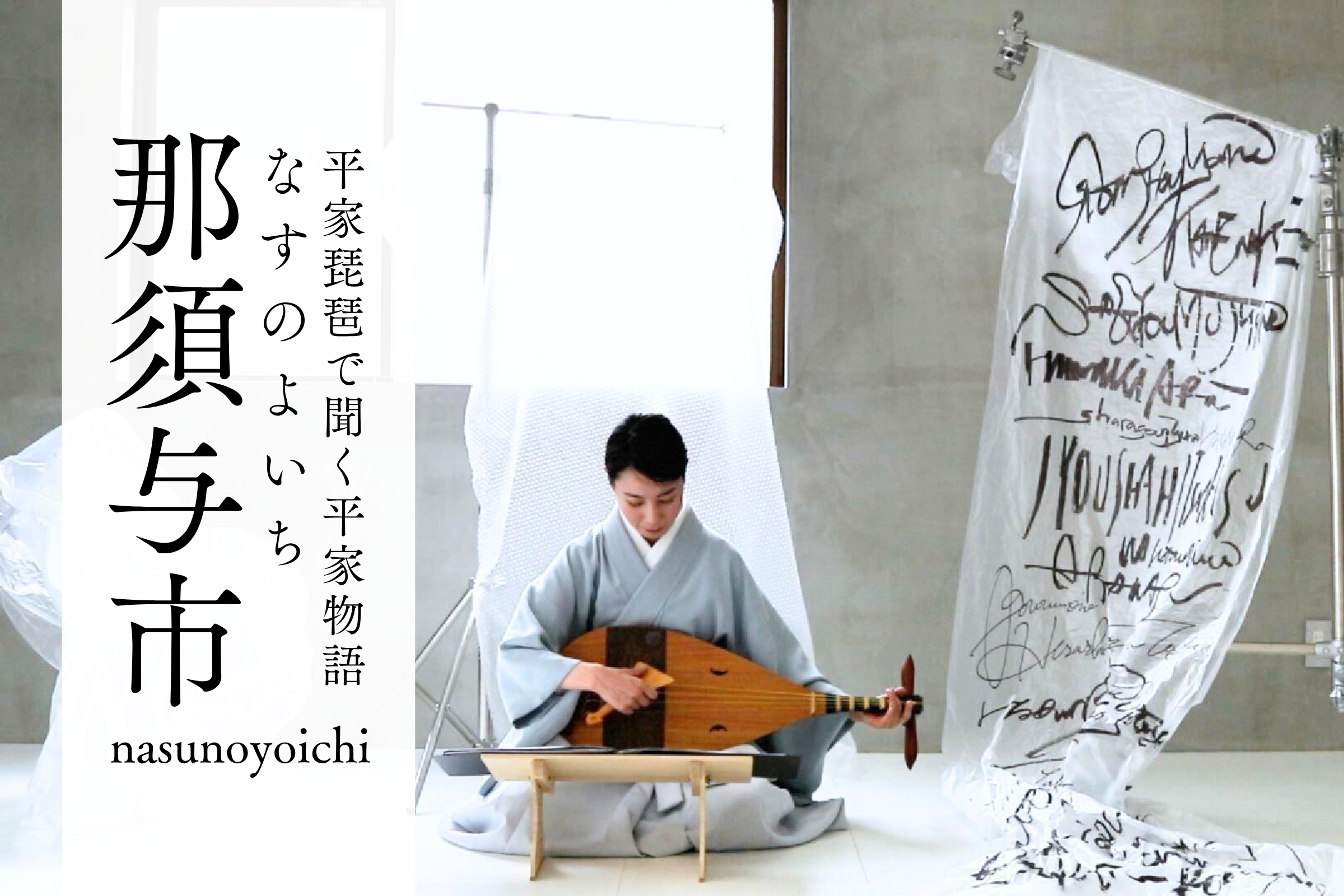 平曲「那須与市」|演奏動画を公開しました
平曲「那須与市」|演奏動画を公開しました -
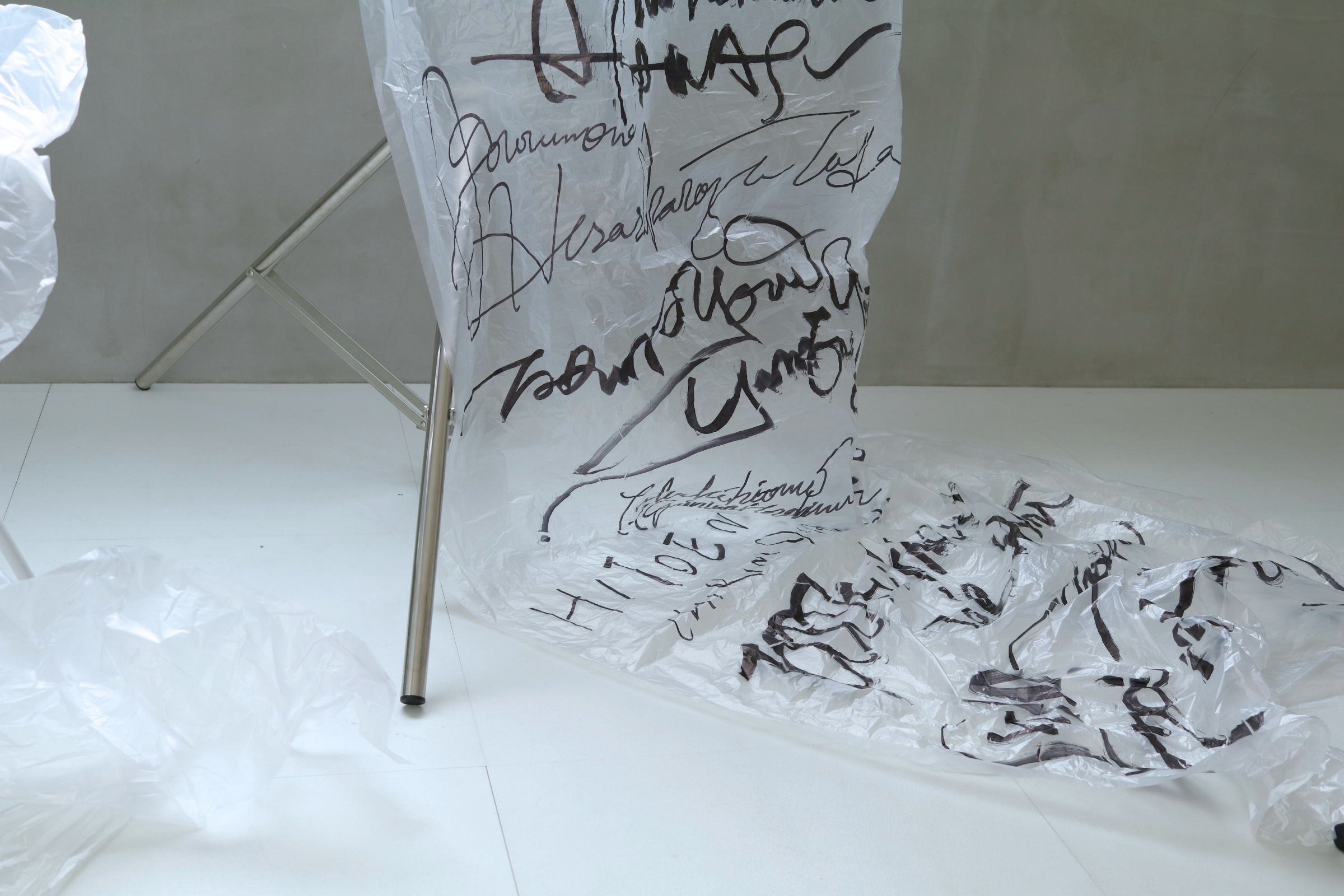 平曲「弓流」「嗣信最期」|演奏動画を公開しました
平曲「弓流」「嗣信最期」|演奏動画を公開しました -
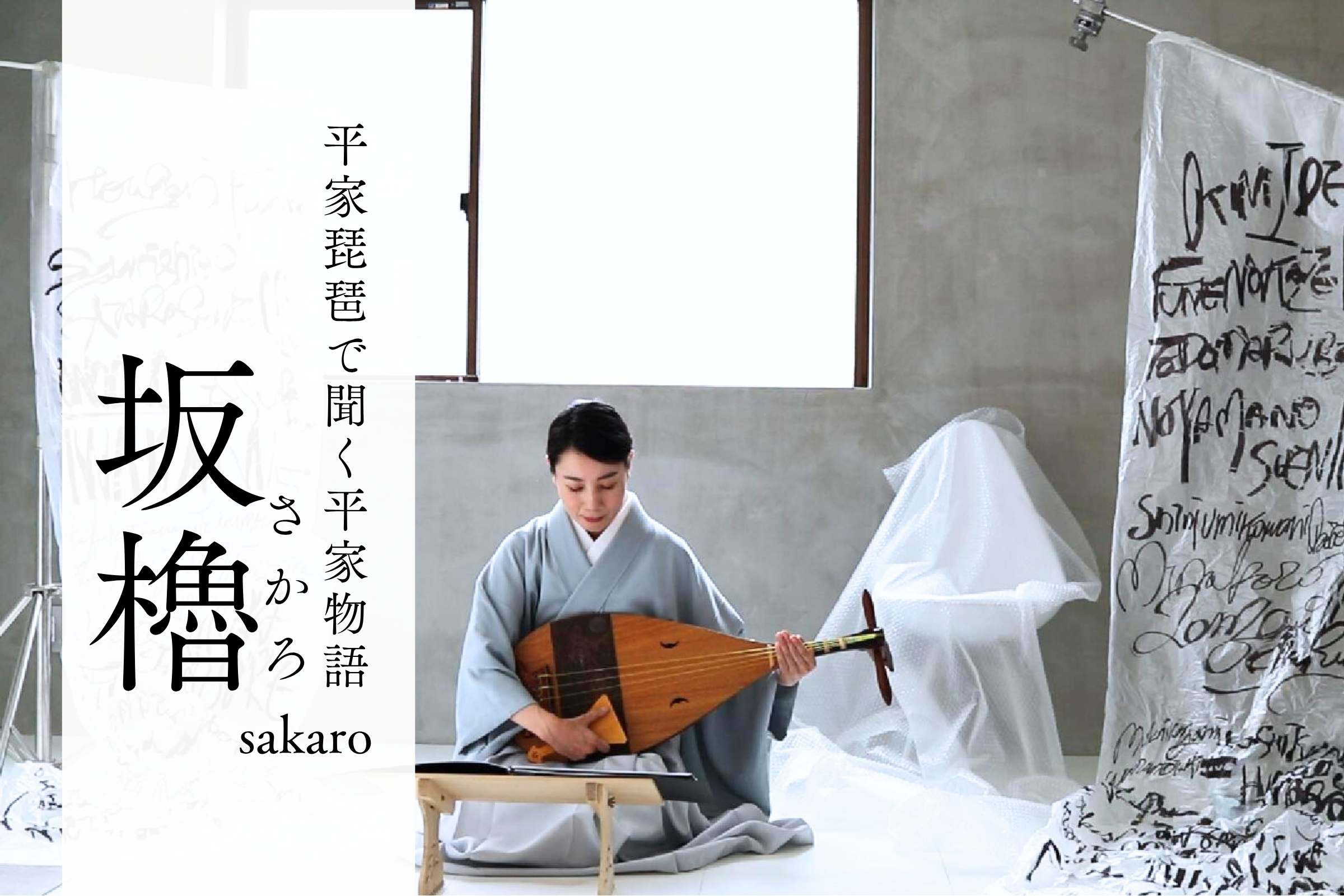 平曲「坂櫓」|平家琵琶で聞く平家物語×インスタレーション一部公開
平曲「坂櫓」|平家琵琶で聞く平家物語×インスタレーション一部公開 -
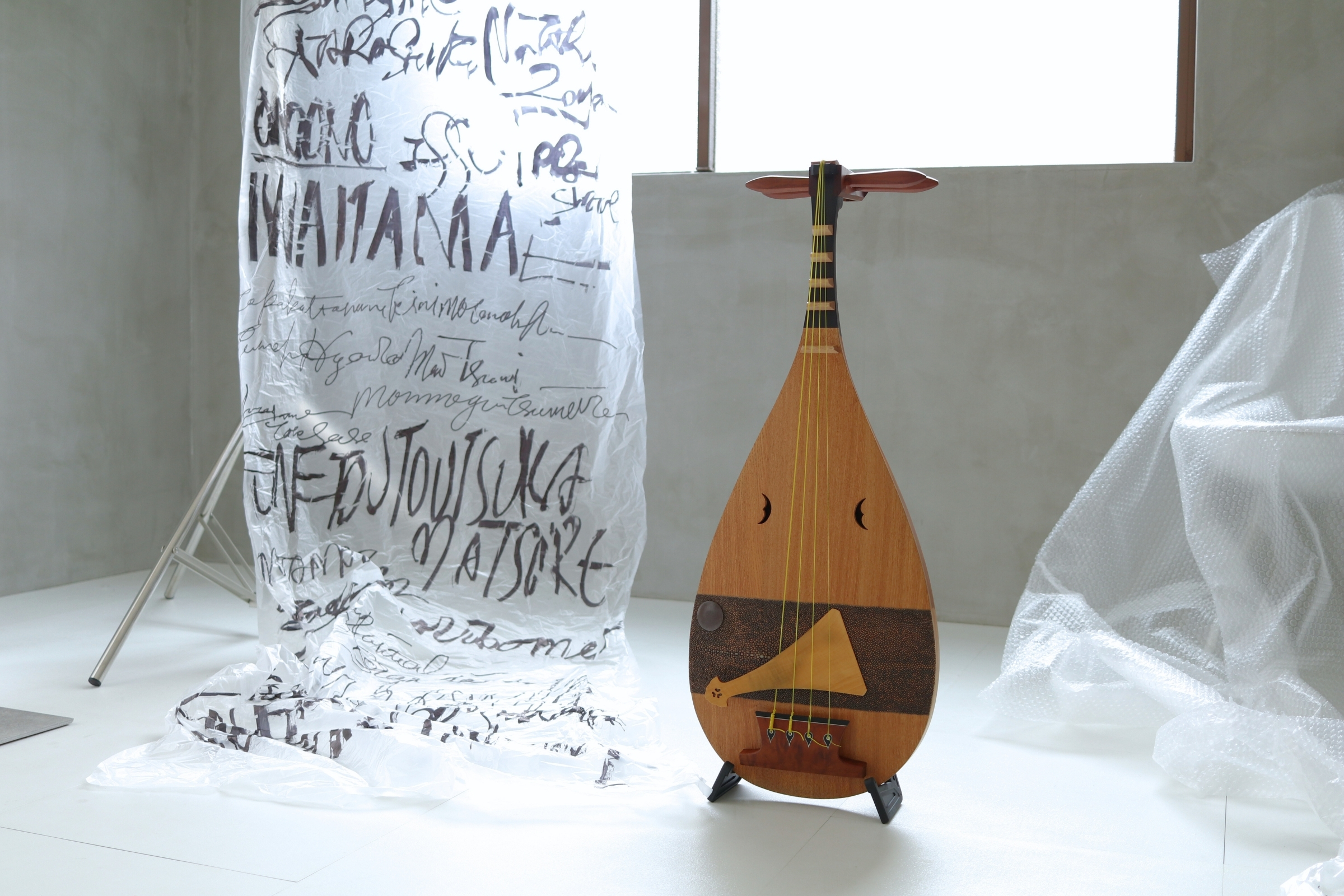 境をめぐるインスタレーション構想公開
境をめぐるインスタレーション構想公開 -
 作品アーカイブページを公開しました
作品アーカイブページを公開しました -
 【その2】インスタレーション×パフォーマンス『終わりの六代』のご案内
【その2】インスタレーション×パフォーマンス『終わりの六代』のご案内 -
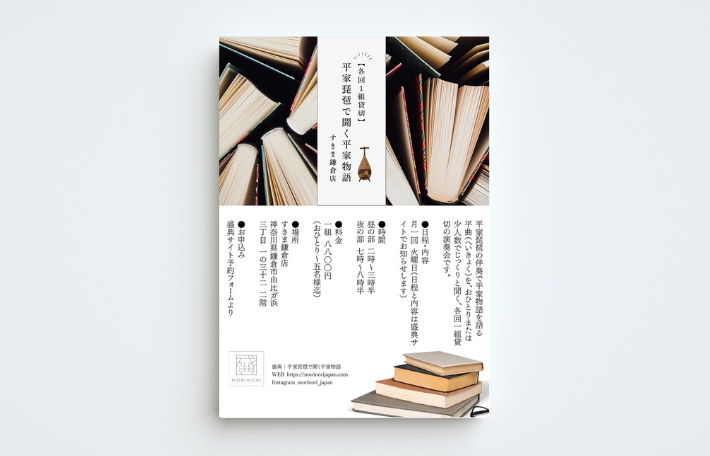 すきま鎌倉店|各回1組|貸切演奏会のご案内
すきま鎌倉店|各回1組|貸切演奏会のご案内 -
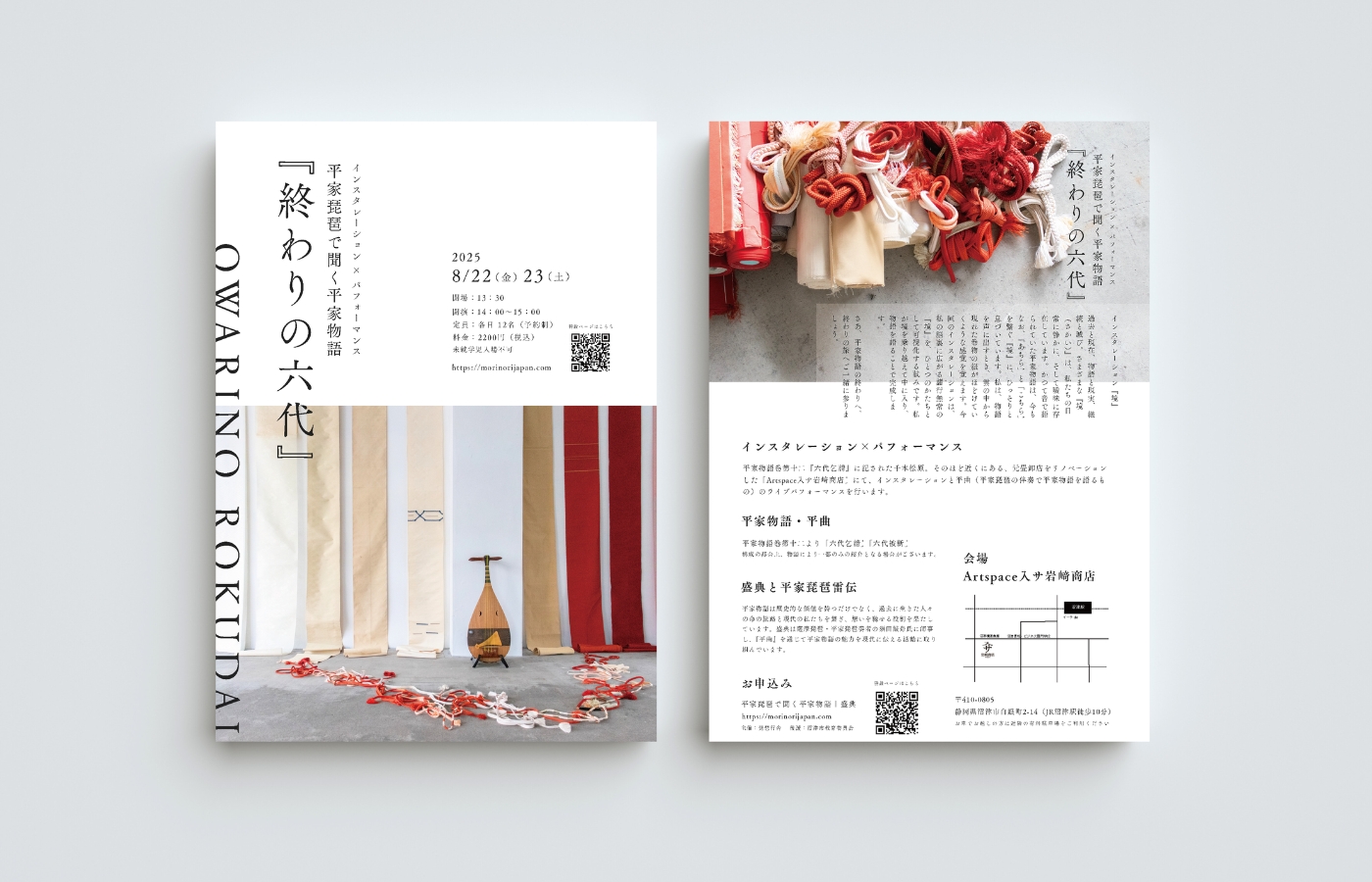 【その1】インスタレーション×パフォーマンス『終わりの六代』のご案内
【その1】インスタレーション×パフォーマンス『終わりの六代』のご案内 -
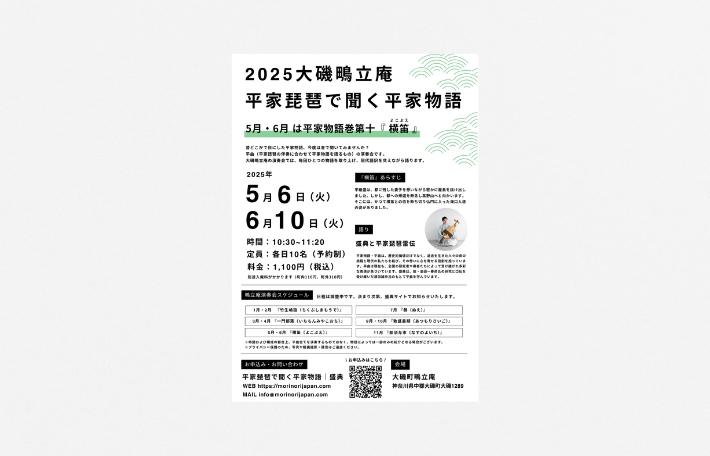 大磯鴫立庵|『横笛』|2025年5月6日・6月10日
大磯鴫立庵|『横笛』|2025年5月6日・6月10日 -
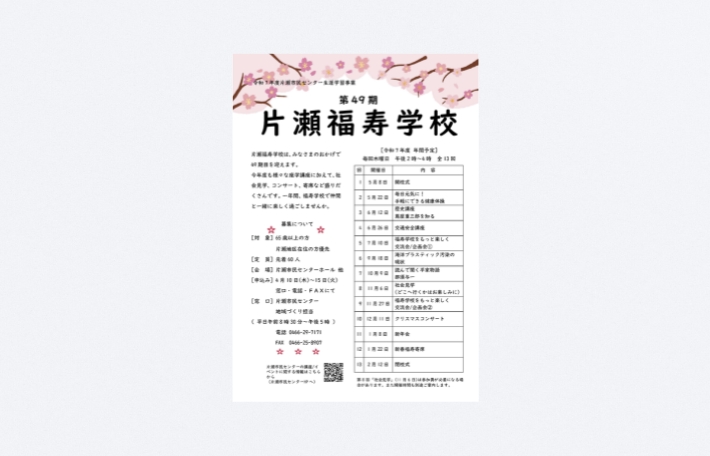 第49期片瀬福寿学校|10月「読んで聞く平家物語」
第49期片瀬福寿学校|10月「読んで聞く平家物語」 -
 下関AIR75滞在と演奏会のご報告
下関AIR75滞在と演奏会のご報告 -
 平家物語の舞台へ ―アーティスト・イン・レジデンスで語る『最期の海、壇ノ浦。』下関版
平家物語の舞台へ ―アーティスト・イン・レジデンスで語る『最期の海、壇ノ浦。』下関版 -
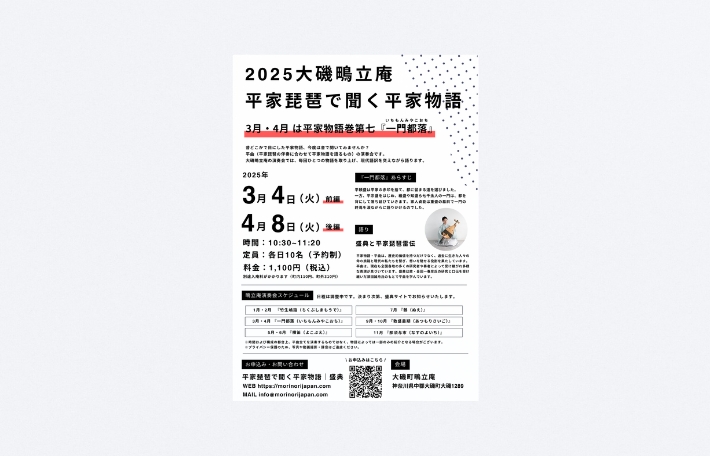 大磯鴫立庵|『一門都落』|2025年3月4日・4月8日
大磯鴫立庵|『一門都落』|2025年3月4日・4月8日 -
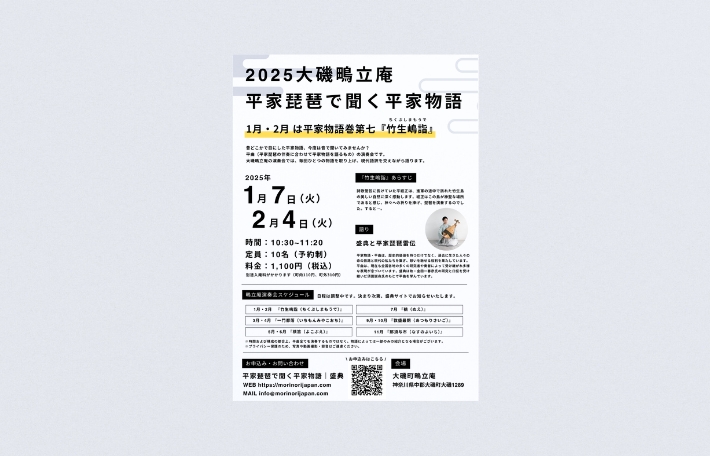 大磯鴫立庵|『竹生嶋詣』|2025年1月7日・2月4日
大磯鴫立庵|『竹生嶋詣』|2025年1月7日・2月4日 -
 【鎌倉版】平家琵琶で聞く平家物語|最期の海、壇ノ浦。
【鎌倉版】平家琵琶で聞く平家物語|最期の海、壇ノ浦。 -
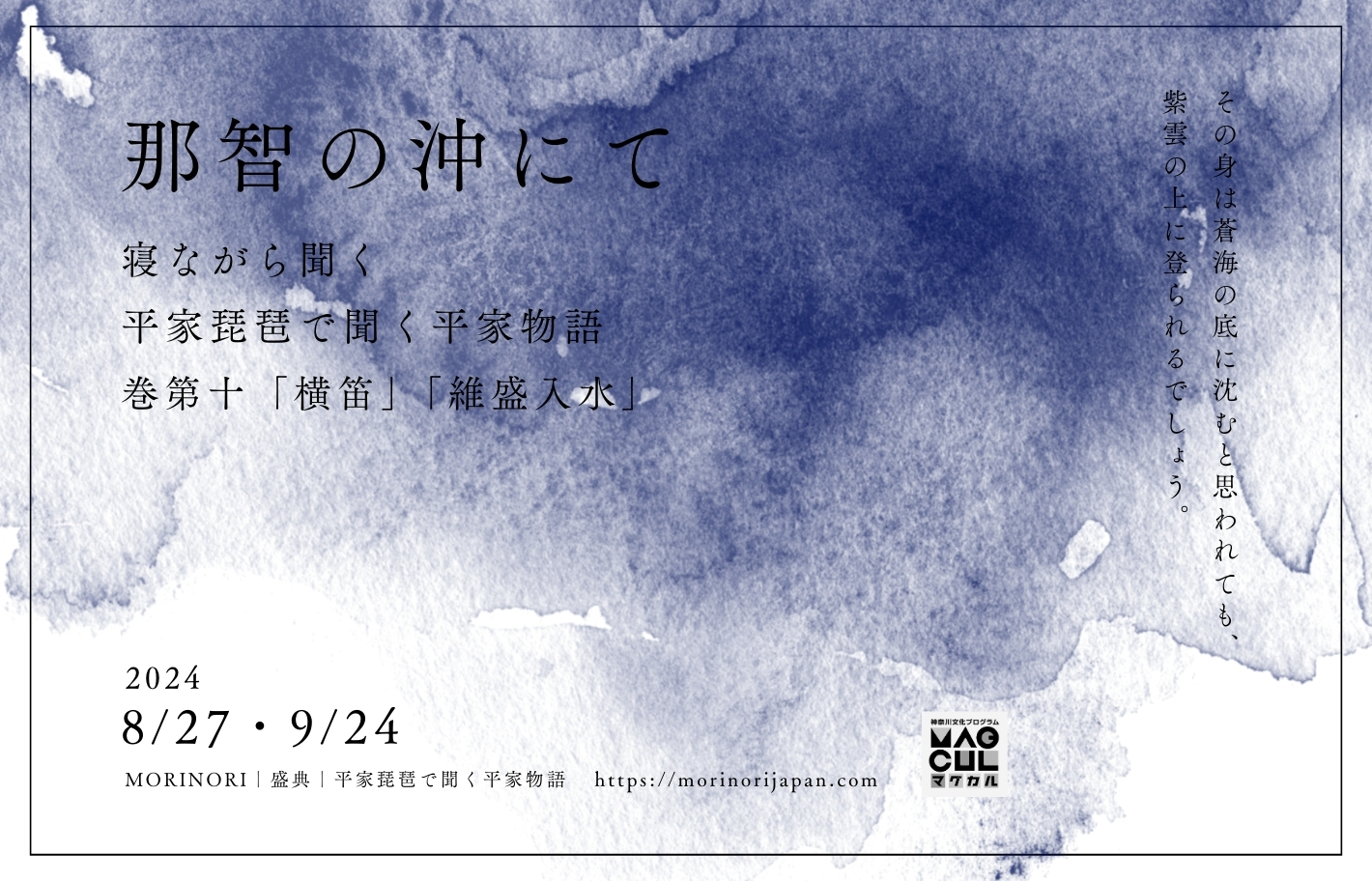 那智の沖にて|寝ながら聞く平家琵琶で聞く平家物語
那智の沖にて|寝ながら聞く平家琵琶で聞く平家物語 -
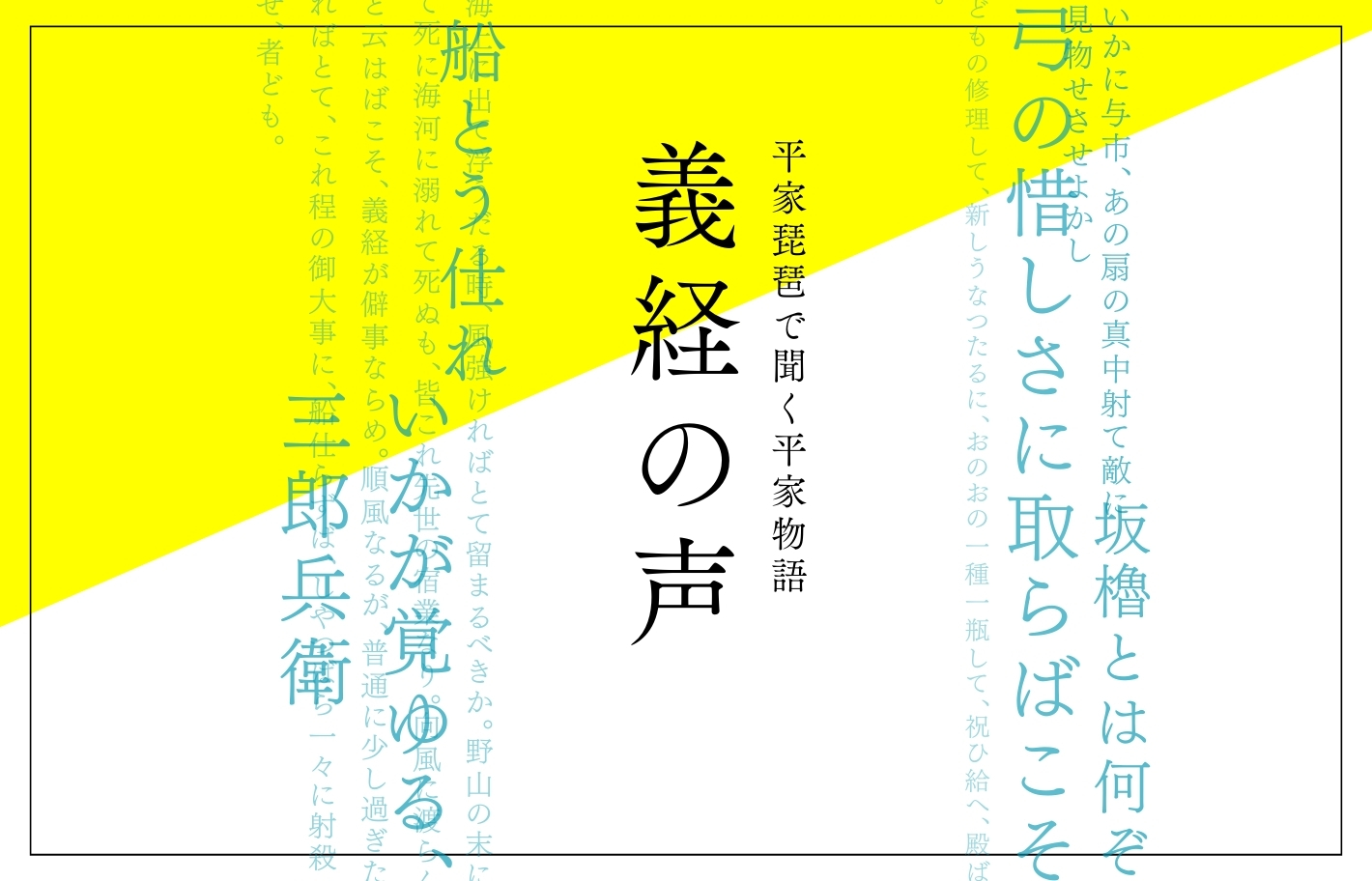 怒る笑う悲しむ脅す義経!【藤沢市後援】義経の声|ショートパフォーマンス版
怒る笑う悲しむ脅す義経!【藤沢市後援】義経の声|ショートパフォーマンス版 -
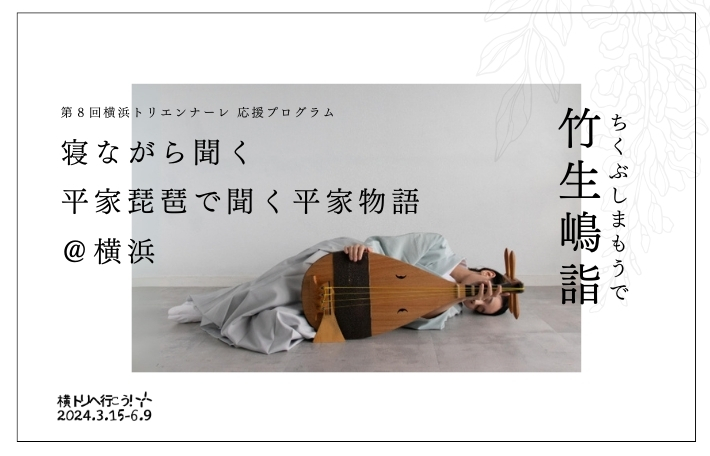 寝ながら聞く|平家琵琶で聞く平家物語@横浜|竹生嶋詣
寝ながら聞く|平家琵琶で聞く平家物語@横浜|竹生嶋詣