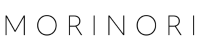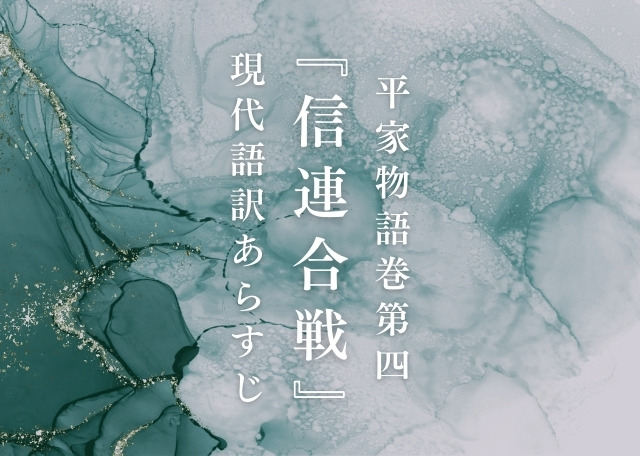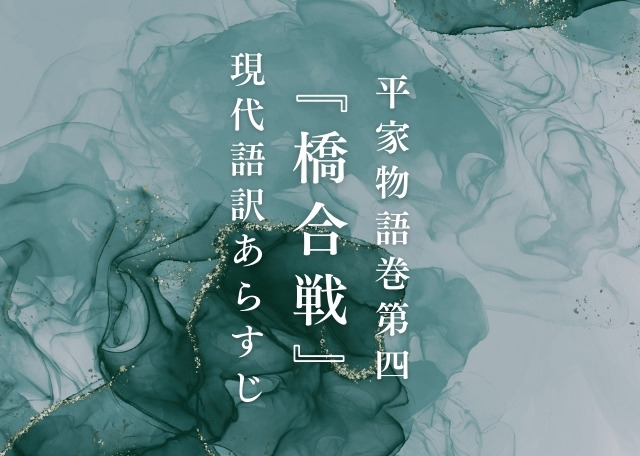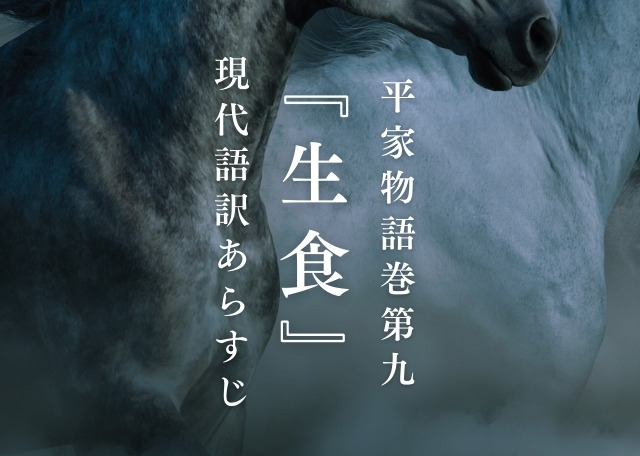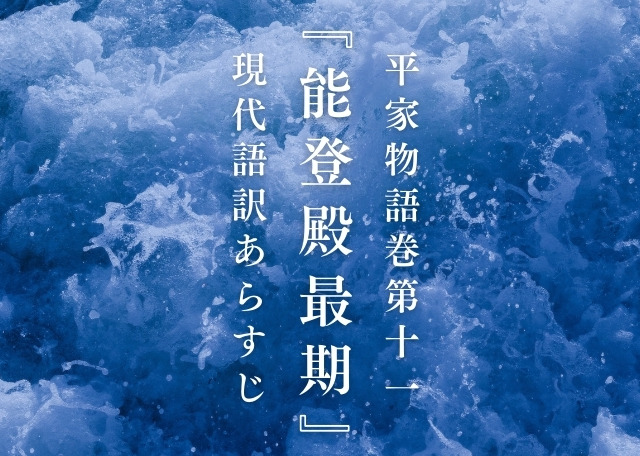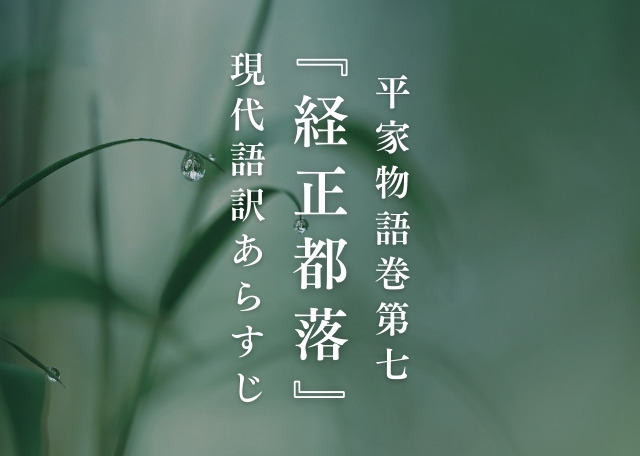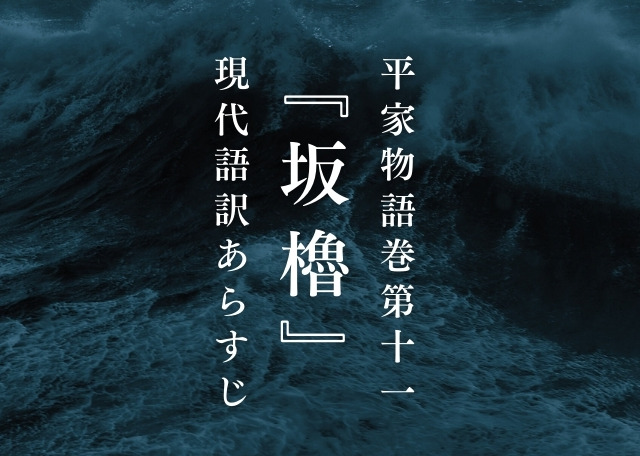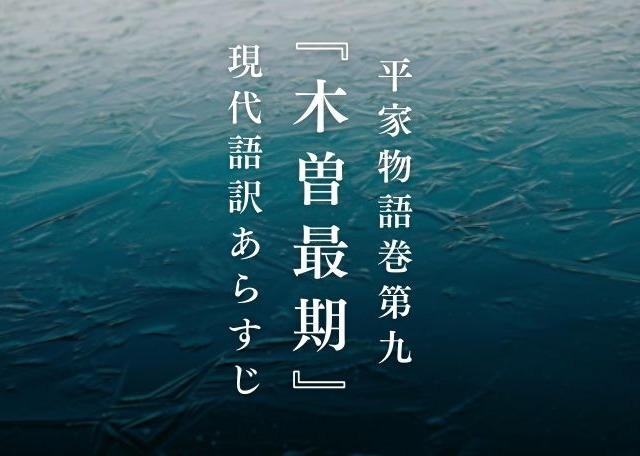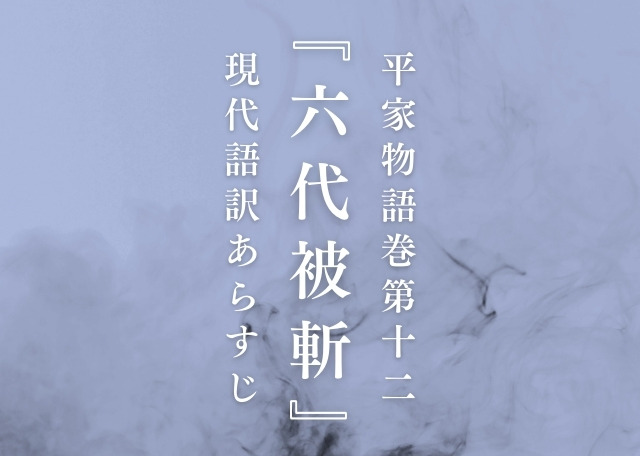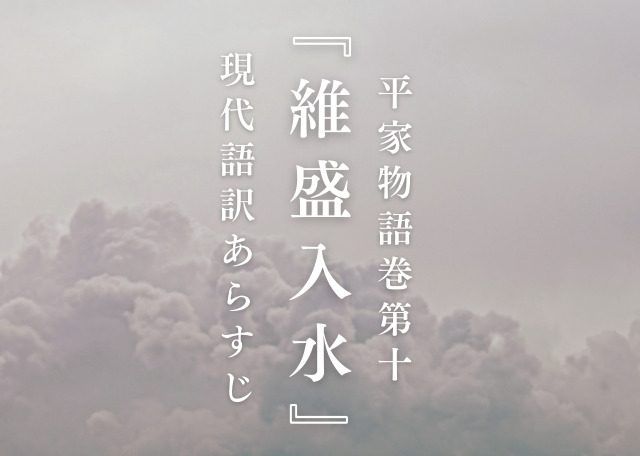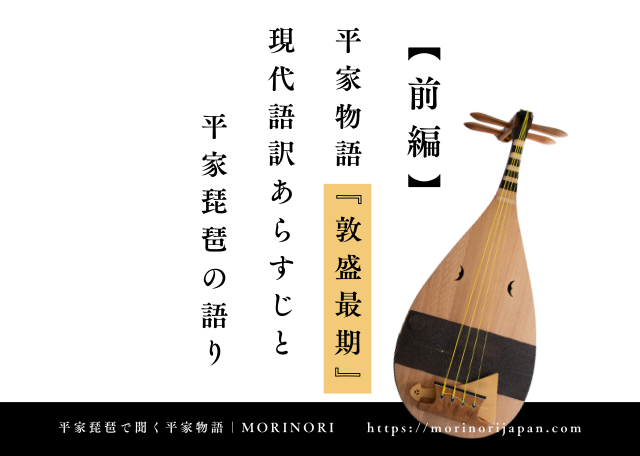ようこそお越しくださいました。
ここは、平曲(平家琵琶の伴奏で平家物語を語るもの)の小さな演奏会や講座を行っている盛典のサイトです。このページでは平家物語巻第四『競(きおう)』の現代語訳あらすじを紹介しています。
▼初めての方へ
https://morinorijapan.com/welcome
▼平曲を聞く
https://morinorijapan.com/tale-of-the-heike-sound-archive
▼平家物語現代語訳一覧はこちら
演奏会や講座等で行う平家物語を現代語訳にしています
https://morinorijapan.com/category/tale-of-the-heike/

平家物語巻第四『競』簡単なあらすじ
源三位入道頼政(源頼政)が以仁王の挙兵を決意するきっかけとなったのは、頼政の子仲綱の愛馬「木の下」を平宗盛が強引に取り上げた一件である。宗盛は木の下に「仲綱」という焼印を押して意図的に乗り回したため、父子の怒りと屈辱は日増しに深まっていった。以仁王の挙兵の折、頼政の郎等・渡辺競は、宗盛に忠誠を誓うふりをし、名馬「南鐐」を与えられた。しかし競は、自邸に火を放って三井寺の頼政のもとへと逃げ帰る。宗盛は激怒して追討を命じたが、剛力無双の武芸の持ち主である競を、誰一人として追うことができなかった。その後「南鐐」は「宗盛入道」と焼印をされて六波羅へ戻された。
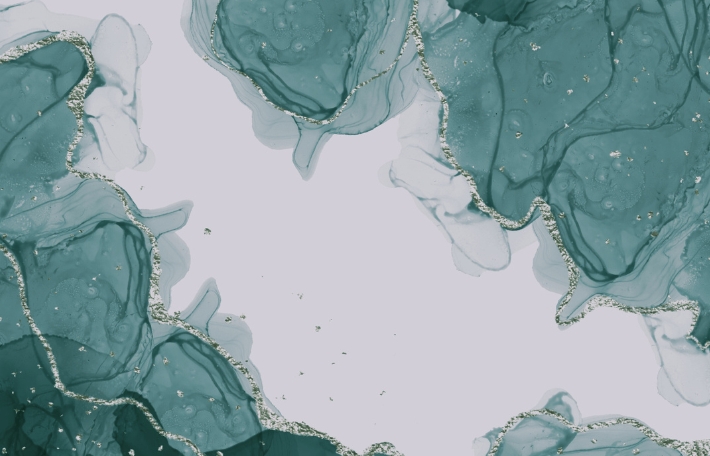
平家物語巻第四『競』現代語訳全文
※平曲の譜面『競』から書き起こした文章を現代語訳にしています
その頃、近衛河原におられた源三位入道頼政は、これまで長年、平穏無事に過ごしてこられたにもかかわらず、今年になってなぜ謀反を起こされたのか。それはひとえに、平家の次男・宗盛卿(平宗盛)の常軌を逸した振る舞いばかりをご覧になっていたからであった。ゆえに、人の世にあって口にしてはならぬことを言い、してはならぬことをするのは、慎み深く、深い思慮を持つ者である。
たとえば、源三位入道頼政の嫡子伊豆守仲綱のもとには、京中でも名高い名馬がいた。鹿毛の毛色で、並ぶ者のないほどの逸物であり、乗り味・走りぶり・気性ともに優れ、まさにこの世のものとは思えぬほどであった。名を「木の下(このした)」といった。この馬の噂を、平家の前右大臣・宗盛卿が耳にして仲綱のもとに使者を立て、「その名馬を一度拝見したく、お譲り願えぬか」と仰せになった。
仲綱は、「確かにその馬は持っておりますが、近ごろあまりに乗りすぎて疲れさせてしまいましたので、しばらく養生させようと思い、田舎に下げております」とお断り申し上げた。宗盛は「それならば致し方ない」と、その後は何の沙汰もなかった。しかし、宗盛に仕える多くの平家の侍たちは口々に「いや、その馬は一昨日もいましたぞ」 「昨日も見かけました」 「今朝も庭で乗っておられましたよ」と言うので、宗盛は「さては、惜しんで譲る意思がないのだな。許せぬ。直ちに馬を差し出すように申し付けよ。」と、家来を次々に走らせては、手紙で日に五、六度、七、八度と求め続けた。
三位入道頼政は、仲綱の元に向かい「たとえ金を丸めて造ったような馬であろうとも、あれほどまでに人がしきりに願うものを、惜しんで渡さぬ道理があろうか。早々にその馬を六波羅に届けるのだ」仲綱は力及ばず、やむなく一首の歌を添えて「木の下」を六波羅に差し出したのだった。
恋しくば来ても見よかし身にそふる影をばいかで放ちやるべき(恋しいと思うのなら、どうか来て見てください。この身に寄り添って離れない影のように、あの馬をどうして手放すことができましょうか。)
宗盛卿は、仲綱の歌には返事もせず「なるほど、馬はまことによい馬である。だが、主(仲綱)が惜しんでいたのが癪に障る。主の名前を焼印にせよ」と、”仲綱”という焼印をして厩に置いた。ある日、客人が来て「名高いその馬を拝見したい」と言うと、宗盛は「その”仲綱め”に鞍を置け、引き出せ、乗れ、打て、はれ」などと命じた。この話を聞いた伊豆守仲綱は、「あの馬は我が身に代えても惜しくないと思っていたものだ。それを権力で無理やり奪われただけでも悔しいのに、さらにその名まで辱められ、仲綱の名が世の笑いものになるとは、まことに耐えがたい」と、深く憤った。三位入道頼政は「なぜこのようなことになるのか。おそらく平家の者たちは、慢心してこのような無礼なふるまいをしているのだろう。だが今は、時を待つべきだ」と。こうして頼政は、自らの行動を控えつつも、後に以仁王(高倉宮)に挙兵を勧めたのだと伝えられている。
これにつけても、世間の人々はこぞって小松の大臣(平重盛)のことを偲び語らない者はいなかった。ある時、重盛が参内のついでに中宮の御方を訪れた際、八尺ほどもある大蛇が、彼の指貫の左の輪を這いまわっていた。しかし重盛は、ここで騒げば女房たちも騒ぎ出し、中宮までも驚かせてしまうだろうと考え、左手で蛇の尾を押さえ、右手で頭をつかむと、それを自分の直衣の袖の中へと引き入れて、何事もなかったかのように立ち上がり、中門の方へ出て行った。そして、「六位やおらぬか、六位や」と声をかけると、そのとき伊豆守仲綱が、まだ衛府の蔵人であったが、「仲綱です」と名乗って参上した。すると重盛は、その蛇を仲綱に授けた。仲綱はこれを受け取り、弓場殿を通って殿上の小庭に出て、御倉の小舎人を呼んで、「これを受け取れ」と言った。しかし大きく頭を振って逃げ去ってしまった。仕方なく仲綱は自分の郎等の競(きおう)という者を呼んで、これを与えると、競はそれを受け取ってそのまま捨てたという。
翌朝、小松殿から立派な馬に鞍を置いて、伊豆守仲綱のもとへ届けられた。「さても、昨日の振る舞いは、たいそう優雅で品のあるものに感じられた。これは“乗り一”の馬である。夕暮れ時、陣外から傾城(愛する女性)のもとへ参られる時に用いるがよい。」と送られたのだった。仲綱は大臣様からの返礼であると、馬をありがたく拝領し「昨日のご振る舞いこそは、まるで『還城楽(げんじょうらく)』そのもののようでございました」と返事を申し上げたという。それにしても、なぜ小松大臣はこれほどまでに優美で品格あるご性格でいらしたのか。それに比べて宗盛卿は、どうしてこうも違っているのだろうか。人が惜しむ馬を無理に乞い取り、それがもとで天下の大事(=以仁王の挙兵、謀反)にまで及ぶような事態を引き起こしたことは、実に嘆かわしいことである。
同じく十六日の夜のこと、源三位入道頼政は、嫡男伊豆守仲綱、次男源太夫判官兼綱、六条蔵人仲家とその子蔵人太郎仲光をはじめとする直甲三百余騎と共に、自らの館に火をかけて焼き払い、三井寺へと向かった。
ここに、頼政に長年にわたって身近に仕えていた郎等で、渡辺源三競の滝口という者がいた。馳せ遅れ、留まっていたところを六波羅に呼び出され、こう問いただされた。「なぜお前は相伝の主である源三位入道に、供をせずに留まっていたのだ」競は畏まって「日頃は、いざという時があれば命を真っ先に差し出すつもりでございました。しかしこの度はどうしたことか、このように知らされないまま、留まっていた次第でございます。」
宗盛卿は、これを聞いて「お前は両方に付き従おうとしているのではないか。後に栄えることを目論んで、この平家に仕えるか。それとも、朝敵頼政法師に心を寄せているのか。ありのままに申せ」と、競は涙をはらはらと流しながら「たとえ長年の主従のご縁があるとはいえ、どうして朝敵となられた方に心を寄せ、従うことなどできましょうか。ただこの殿中に奉公いたします。」それを聞いた宗盛卿は、「では忠義を尽くせ。頼政法師が与えてくれた恩には決して劣らぬ恩を与えようぞ」と言い残し、屋敷の中へお入りになった。
ややあって「競はおるか、競はおるか」と呼ばれて、競は「おります」と応じながら、その日は朝から夕方に至るまでそばに控えていた。日もようやく傾きはじめたころ、宗盛卿がようやくお出ましになった。競はかしこまって申し上げた。「まことに、三位入道殿が三井寺におられると伺っております。きっと討伐の兵も向かわせられることでしょう。三位入道と縁のある者としては、渡辺党、そして三井寺の僧兵たちがいるのではないかと存じます。選り討ちを果たしたいと考えておりますが、乗って出陣すべき馬を持っておりましたところ、近頃渡辺の親しい者に盗まれてしまいました。そこで、御馬を一匹、拝領できればと存じます。」これを聞いた宗盛卿は、それはもっともだと、かねてから大切にしていた白葦毛の馬で、南鐐(なんりょう)という名の秘蔵の馬に、立派な鞍を置いて競に与えた。競はそれを賜って自分の宿所に戻り、早く日が暮れないものか、三井寺へ駆けつけて、入道殿の先駆けとして討ち死にを遂げようと決意したのであった。
日もようやく暮れると、競は妻子たちをそれぞれの場所に密かに身を隠させ、三井寺へと出立した。その心の中は、なんとも残酷哀れであった。その日の装束は、狂紋の狩衣に、菊綴を大きくつけたものに代々伝わる着背長、緋色威の鎧を着込み、星白の甲の緒を締めていた。厳めしい太刀を差し、二十四本もの切府の矢を負っていた。さらに、滝口(宮中警護の武士)としての本分を忘れまいとしてか、鷹の羽根で矧いだ美しい的矢一束を添えて背負った。そして、滋籐を巻いた弓を脇に挟み、南鐐にまたがり、乗り換え用の馬一頭を伴わせ、舎人の男に盾を脇に構えさせ、自邸に火をかけて焼き払ったうえで、三井寺へと馳せていった。
六波羅では、競の館から火が上がったと騒然としていた。宗盛卿もあわてて外に出て、「競はいるか」と尋ねると、「すでに姿がございません」との返答だった。宗盛卿は「あの者に裏をかかれたか」と怒り、「侍ども、追いかけて討て」と命じた。しかし、競は名が知られた剛力無双の武士であった。並外れた体力と、立て続けに矢を射る腕前の持ち主で、背に負った二十四本の矢を放てば、まず二十四人は射殺されてしまうに違いない。そのため兵たちは「下手に音を立てるな、静かにしていよう」と囁き合い、誰ひとり追いかけようとはしなかった。
三井寺では、三位入道の一族や渡辺党の者たちが集まっていて、競についての話し合いが行われていた。皆「どうにかして競を召し連れてくるべきでしたのに、今ごろどんな目に遭っていることか」と口々に話していた。すると、三位入道は「競は私に深い忠義を持つ者だ。あの者が、簡単に敵に捕らえられるようなことはない。今見ていろ、今にきっとここへ来るぞ」と、その言葉が終わらぬうちに競がすっと参上したので「それ見たことか」とおっしゃった。
競は畏まって「伊豆守殿(源仲綱)の木の下の代わりに、六波羅から南鐐奪って参りました」と、南鐐を差し出した。伊豆守はこれをとても喜ばれ、すぐにその馬の尾髪を切り取り、焼印を押して次の夜、六波羅に送り返した。夜半ごろ、門の中に追い入れられた馬は、厩に入って他の馬と餌を取り合い始めた。すると、舎人が驚いて「南鐐が戻ってきました」と言うので宗盛卿が急いで出て見に来ると、「昔は南鐐今は平の宗盛入道」という焼印が付けられていた。
「憎たらしい競め、まんまと騙しおって。次に三井寺を攻めるときには、何としてでもあの競を生け捕りにして、鋸で首をはねてくれよう」と、怒りに任せて何度も跳ね回りながら言ったが、その後も南鐐の尾髪は生えず、焼印も消えることはなかったという。
→次のお話『橋合戦』はこちら
https://morinorijapan.com/tale-of-the-heike/hashigassen
→前のお話『信連合戦』
https://morinorijapan.com/tale-of-the-heike/nobutsurakassen
▼平家物語現代語訳一覧はこちら
※演奏会や講座等で行う平家物語を現代語訳にしています
https://morinorijapan.com/category/tale-of-the-heike/
ここまでご覧いただきありがとうございました。
いつかどこかでお会いできますように。