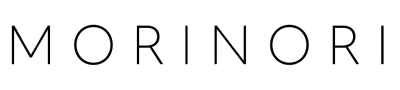平家一門|平家物語巻第七『一門都落』現代語訳あらすじ

『一門都落』簡単なあらすじ
平家が都を落ち延びる中、頼盛は池殿に火を放ち離れるが途中で引き返す。その行動に疑念を抱いた兵が大臣殿に矢をかけることを進言するも叶わなかった。新中納言知盛は先行きを悲観し、都で最期を覚悟すべきだったと嘆く。落ち延びる一門は大臣宗盛をはじめ、維盛や知盛、教盛ら七千余人。残党として辛うじて生き延びた者たちであった。
一方、肥後守貞能は源氏の待ち伏せと聞き、迎え撃とうとするが誤報と知り引き返す。大臣殿に都で最期を迎えるべきだと進言するが、大臣殿が義仲の進軍と法皇の崩御を理由に西国へ向かう意図を示したため、貞能は暇を得て都へ戻った。貞能は重盛の墓を掘り起こし、涙ながらに一門の終焉を嘆く。一門はそれぞれが後ろを振り返りつつも散り散りに落ち延び、相伝の絆や恩義を忘れられぬまま、涙ながらの別離を繰り広げた。

平家物語巻第七『一門都落』現代語訳あらすじ
※平曲の譜面『一門都落』から書き起こした文章を現代語訳にしています
池の大納言頼盛の卿は、池殿に火を放ちその場を立ち去られたが、鳥羽の南の門に差し掛かった時、急に思い出したことがあると言い、鎧に付けていた赤印をすべて剥ぎ取り、率いていた三百余騎の兵を連れて都へ引き返した。これを見た越中次郎兵衛盛嗣は急いで馬から飛び降り、大臣殿(平宗盛)の御前に畏まり「あれをご覧ください。池殿が留まられたため、多くの侍たちもその場に留まっております。この状況は不審に思われます。恐れながら、一矢放つべきではないでしょうか。」大臣殿はこれを聞き、「長年恩を受けている身でありながら、このような時に見限るとは、そのような者は放っておけばよい」と言い、矢を射ることを許さなかった。
「ところで、小松殿の君達(平維盛)はどうしているのか」と尋ねると、「まだ一人としてお姿が見えません」との返事があった。大臣殿は「都を出発してまだ一日も経たないうちに、人々の心がこれほどまでに変わり果てていくとは、なんと情けないことだ」と嘆かれた。これを聞いた新中納言知盛の卿は、「西国に向かったところで、きっと同じようなことが起こるに違いない。だからこそ、都の内でどのような結果になろうとも覚悟を決めるべきだと申し上げたのだ」と、大臣殿を恨めしそうに見つめた。
そもそも池殿(平頼盛)が都に留まられたのは、鎌倉の兵衛佐頼朝が平素から池殿に特別な情をかけ、その存在を深く敬っていたからである。ひとえに故池殿(池禅尼)の恩に報いようとする思いからであった。頼朝は「恩義を忘れることはない。もしその誓いに背くようなことがあれば、八幡大菩薩の罰を受けよう」と度々誓状をもって述べていた。そして、平家討伐の討手の使者が来るたびに、池殿の侍に対しては決して弓を引くなと念を押し、その誠意を示していた。こうした事情から、一門の平家が都を落ち延びる中、池殿は兵衛佐頼朝に助けてもらえるだろうと期待し、都に留まることを選ばれたのである。
八条の女院は、都を襲う戦乱を恐れ、仁和寺の常盤殿に身を隠していた。頼盛の卿がこの女院とともにあったのは、女院の乳母宰相殿という女房に連れ添っていたためである。女院に向かい、「万一のことがあれば、どうか頼盛をお助けください」と申し上げたが、女院は「今となっては世が変わり果ててしまい、もはや頼るべきものもない」と心細げにお答えになった。頼盛は、頼朝が自分に特別な情をかけてくれるとはいえ、他の源氏たちがどう思うかは分からず、不安を抱いていた。一門を引き離れて都に留まることになったものの、それは波にも磯にもつかず漂うような心地で、心中穏やかではなかった。
やがて小松殿の君達兄弟六人、その勢一千余人が淀の六田河原にて行幸に追いついた。大臣殿はこれを見て喜び、「なぜ遅参したのか」と尋ねると、三位中将(平維盛)は、「幼い子どもたちがあまりにも私を慕い、泣きすがっておりましたので、それを何とか落ち着かせようとしている間に、思いがけず遅れてしまいました」と申し上げた。これを聞いた大臣殿は、「なぜ六代殿(維盛の子)を連れて来なかったのだ」と問いただすと、三位中将は「行く末も頼りなく思われますので」と涙を流した。
落ち延びていく平家の一門は次の者たちである。前の内大臣宗盛、大納言時忠、中納言教盛、新中納言知盛、修理大夫経盛、右衛門督清宗、本三位中将重衡、小松三位中将維盛、新三位中将資盛、越前三位通盛、殿上人には内蔵頭信基、讃岐中将時実、左中将清経、少将有盛、丹後侍従忠房、皇后宮亮経正、左馬頭行盛、薩摩守忠度、能登守教経、武蔵守知章、備中守師盛、淡路守清房、尾張守清定、若狭守経俊、経盛の子大夫平敦盛、蔵人の大夫業盛、兵部少輔正明。
僧には二位の僧都栓真、法勝寺の執行能円、中納言律師仲快、経誦坊の阿闍梨祐円。武士には受領検非違使衛府諸司の尉百六十人。総勢七千余人。これは、この三年間に東国や北国で繰り返された戦いで討ち漏らされ、辛うじて残った者たちである。
平大納言時忠は、山崎の関戸の院に御輿を安置し、男山の方角にひれ伏して拝み、「南無帰命頂礼八幡大菩薩。願わくは、君をはじめとして我らをもう一度故郷へ帰らせ給え」と祈られた。その姿は見る者の胸を深く打つものがあった。それぞれ背後を振り返れば、霞のかかった空を見るような心地がし、故郷の焼け跡から立ち上る煙がひどく心細く思われた。
平中納言教盛「はかなしな 主は雲井に別るれば 宿は煙と立ち上るかな」 はかないものだ。家の主は雲の彼方へ旅立ち、家は煙となって消えていく。
修理大夫経盛「故郷を 焼野の原と顧りみて 末も煙の 浪路をぞ行く」 焼け野原と化した故郷を振り返り、この先は煙のような波路を進むばかりだ。
故郷を一片の煙として眺めつつ、果てしない雲路の先へ向かう彼らの心中は、推し量るに余りあるほどの哀れさであった。
肥後守貞能は、川尻で源氏が待ち構えていると聞き、その勢五百余騎を率いて迎え撃とうとしたが誤報と分かり、急ぎ引き返した。そして宇度野の辺りで行幸の一行に出会うと大臣殿の御前に駆け寄り「これは一体どちらへ向かわれるおつもりでしょうか。もし西国へ下られたとしても、落人としてあちらこちらで討たれ、憂き名を流されるだけのこととなりましょう。それよりは、都の内に留まり、いかなる結果になろうとも、ここで覚悟をお決めになるべきではないでしょうか。」と言った。
大臣殿は、「貞能はまだ知らぬのか。木曽義仲がすでに北国より五万余騎を率いて攻め上り、天台山東坂本を軍勢で埋め尽くしている。法皇も昨夜のうちにお隠れになった。せめて行幸だけでも無事に終わらせ、いっときの猶予を得たいと考えているのだ。」貞能はこれを聞き、「そうでございましたら、貞能は暇を賜り、都の内でどうにでもなりましょう」と申し出た。そして、自らの率いていた五百余騎の兵を小松殿の君達たちに付け、自身は手勢三十騎を率いて都へ戻った。
平家の残党を討つために貞能が都に戻ってきたという噂が広まると、池の大納言頼盛の卿は、自分のことに違いないと思い込み、大いに恐れ騒ぎ立てた。貞能は西八条の焼け跡に大幕を張り、一夜を過ごした。しかし、平家の君達たちは誰一人として戻らず、行く末を案じて心細く感じていた。源氏の軍馬の蹄に踏みにじられることを避けるため、貞能は小松殿(平重盛)の墓を掘り、御骨に向かって、まるで生きた人に語りかけるように涙を流しながら語りかけた。
「ああ、なんと痛ましいことでしょう。一門の終焉をご覧ください。生ある者は必ず滅び、喜びの後には必ず悲しみが来るということは古くから語られていることですが、実際にこのようなことが起こるとは思いもよりませんでした。君(重盛)はこのような結末を予見されて、仏や神、三宝に祈りを捧げ、御世を早く終わらせられたのは、誠にありがたいことでございました。貞能もその時、どうにかして後生にお供するべきであったのに、むなしく命を長らえ、このような悲惨な現実に直面してしまいました。せめて、死後は必ず同じ浄土へお迎えください」と、涙ながらに御骨を高野山に送り、墓の土を賀茂川に流した。
その後の行く末に希望も持てぬまま、主君と背中合わせに東国へ落ちていった。貞能は以前、宇都宮(朝綱)に厚情をかけており、宇都宮を頼りに下向した。これが縁となり、再び手厚く迎えられたと伝えられる。
小松の三位中将維盛の卿を除き、大臣殿をはじめとする妻子を伴い落ち延びる者もいたが、次位以下の人々はそうした者たちを引き連れることもできず、後に会う約束を交わすこともかなわぬまま、皆見捨てられる形で下向していった。人は、いずれの日か、いずれの時かに必ず戻ってくると期日を定めても、その日までの時間は非常に長く感じられるものだ。それにもまして、今回の別れは今日を最後、今を限りとするものであるゆえに、行く者も留まる者も互いに袖を濡らして別れを惜しんだ。
相伝の絆や、長年の恩義を忘れることなどできようはずもなかったが、老いも若きも心はひたすら後ろを振り返り、先へ進む足も止まるばかりであった。ある者は磯辺に波を枕に八重の潮路で日を暮らし、またある者は遠くを目指し嶮しい道を越えて馬を駆ける者もいれば、舟を操る者もいた。それぞれがそれぞれの思いを胸に秘めながら、散り散りに落ち延びていったのである。
ご案内
演奏会で語る平曲を現代語訳にしています。
▶平家物語現代語訳一覧
平家琵琶の伴奏で平家物語を聞いてみませんか。
▶演奏会一覧
▶平曲を聞く