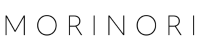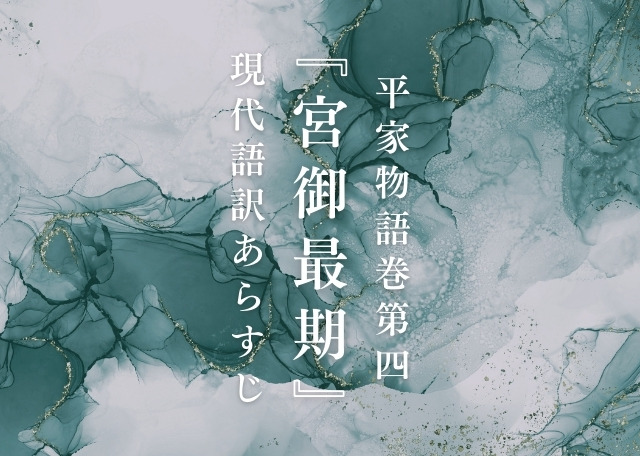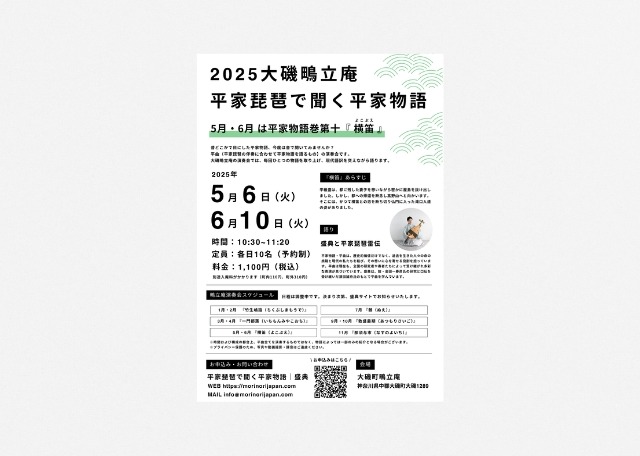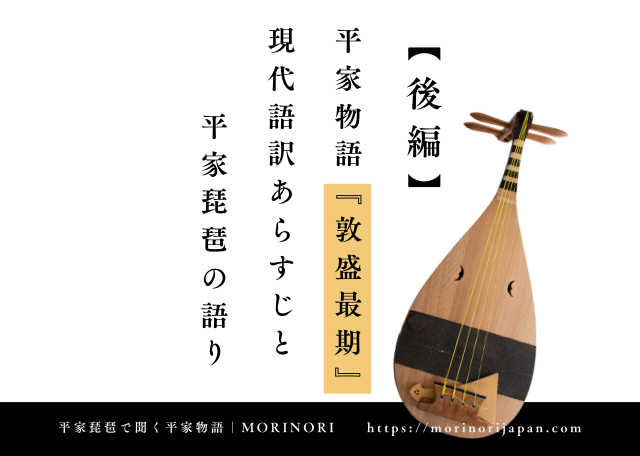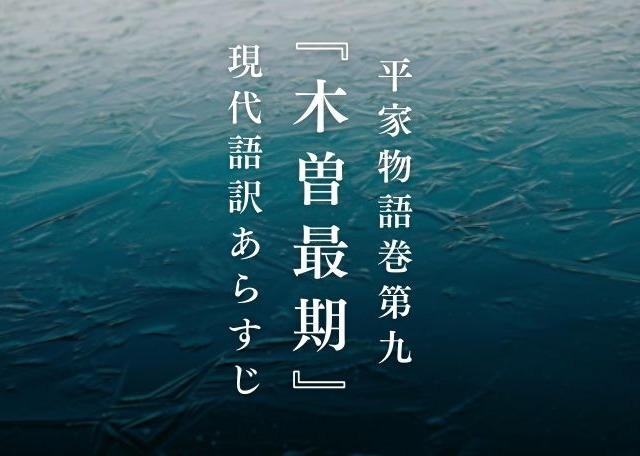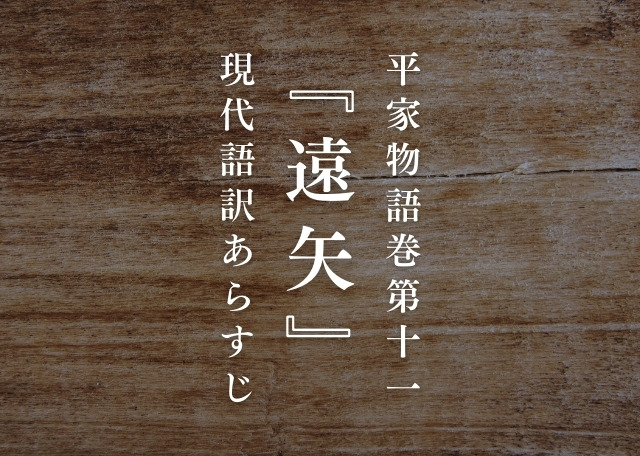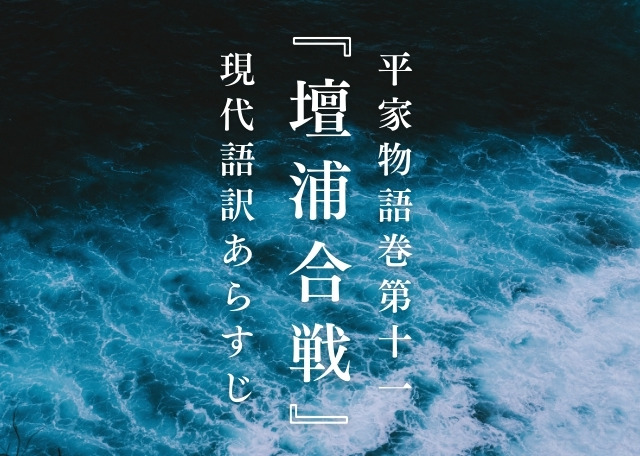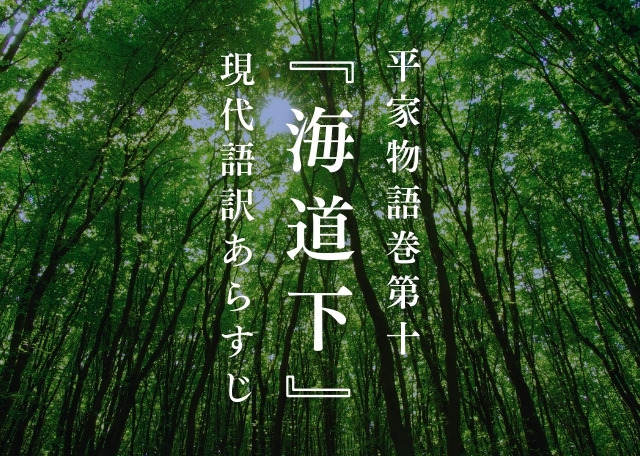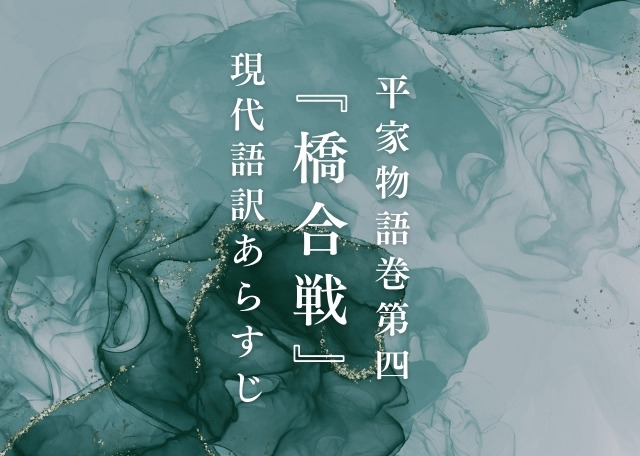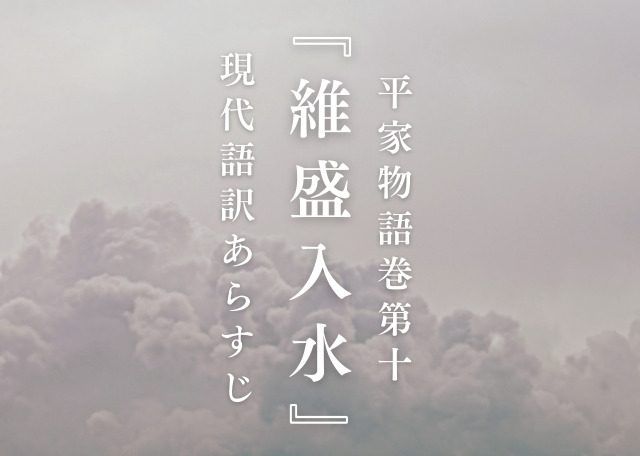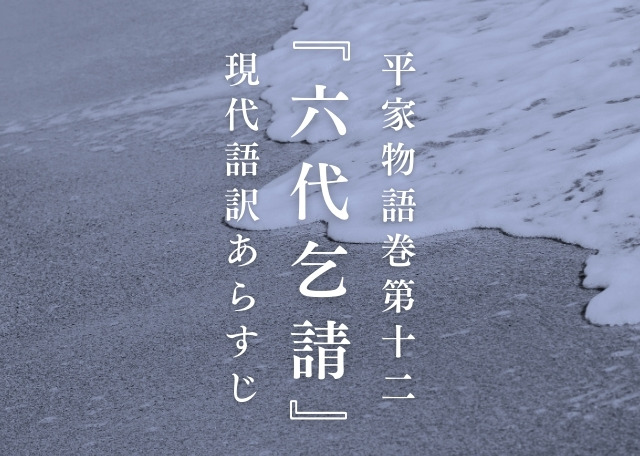ようこそお越しくださいました。
ここは、平曲(平家琵琶の伴奏で平家物語を語るもの)の小さな演奏会や講座を行っている盛典のサイトです。このページでは平家物語巻第四『鵺(ぬえ)』の現代語訳あらすじを紹介しています。
▼初めての方へ
https://morinorijapan.com/welcome
▼平曲を聞く
https://morinorijapan.com/tale-of-the-heike-sound-archive
▼平家物語現代語訳一覧はこちら
演奏会や講座等で行う平家物語を現代語訳にしています
https://morinorijapan.com/category/tale-of-the-heike/
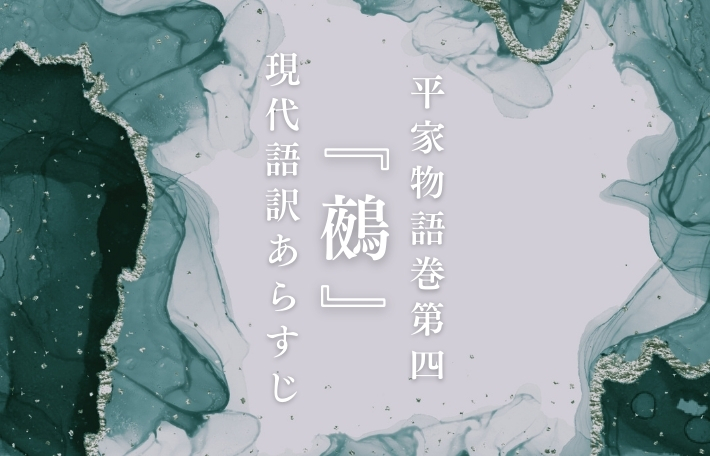
平家物語巻第四『鵺』簡単なあらすじ
源三位入道頼政は、保元・平治の乱で忠義を尽くし数々の戦功を挙げたが、恩賞には恵まれなかった。老いて和歌によって昇殿を許され、三位に叙せられて出家する。頼政は昔、近衛院を悩ませる怪異・鵺(ぬえ)を弓矢で討ち取り、その武勇と歌才を讃えられた。続く二条院の御代にも再び鵺を射止め、重ねて恩賞を受け、名声を確立する。順風な晩年を送るはずだったが、以仁王と共に謀反を起こし、自らも一族も滅びを迎えたのだった。
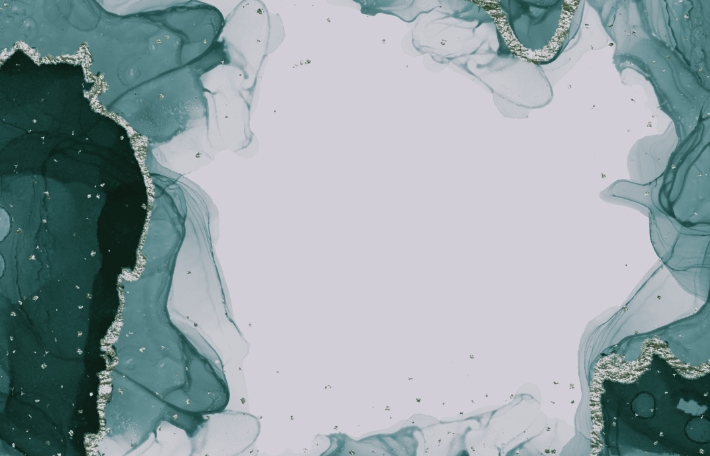
平家物語巻第四『鵺』現代語訳全文
※平曲の譜面『鵺』から書き起こした文章を現代語訳にしています
そもそもこの源三位入道頼政は、摂津守頼光から数えて五代目の三河守頼綱の孫であり、兵庫頭仲正の子であった。去る保元の乱では朝廷側として真っ先に戦功を挙げたが、特に目立った恩賞を預からず、平治の乱でも親類を捨てて参戦したものの、やはり報奨は薄かった。長く大内守護として仕えていたが、昇殿は許されずにいた。歳を重ねて老いが身に迫ってから、心中の思いを込めた和歌を一首詠み、ようやく昇殿を許されたのであった。
人知れぬ大内山の山守は 木がくれてのみ月を見るかな (人目に触れぬ大内山に住む山守の私は、木陰からひっそりと月を眺めるばかりです)
この歌によって昇殿が許され、正四位下としてしばらく仕えていたが、なお三位の位を望み続けて、
上るべき便りなき身は木のもとに 志ひをひろひて世を渡るかな (昇進の望みもない我が身は、木の下でしいを拾い集めるように、わずかな志でこの世を生きているのです)
この歌により三位に昇り、やがて出家して源三位入道頼政と号し、今年で七十五歳になっていた。
この頼政の、生涯における功績と思われる出来事は、去る仁平の頃のことであった。近衛院が在位しておられた時、主上(天皇)は夜ごとに何かに怯えられることがあった。有名な高僧や貴僧たちに命じて、大法や秘法を修させたが、その効果はなかった。怯えられるのは、いつも丑の刻頃のことで、東三条の森の方から黒雲が一塊立ち上がって来て、御殿の上を覆うと、必ず主上は怯えたのであった。
このことによって、公卿たちの間で詮議が行われた。かつて寛治の頃、堀川院が御在位の時も、同じように主上が夜な夜な怯え、取り乱されることがあった。その時の将軍には源義家朝臣がお仕えしており、南殿の大床に控えていた。主上の御悩(天皇の夜ごとの不安)の刻限になると、義家は弓の弦を三度鳴らし、その後、高らかに「前の陸奥守源義家であるぞ」と大声で叫んだ。これを聞いた人々は身の毛もよだつ思いであったが、そのおかげで主上の御悩は治まられたという。そのため、先例に従って武士に命じて警護を行わせるべきだということになり、源氏・平氏両家の兵から選ぶこととなった。そして、この頼政が選び出されたのである。
頼政はその時、まだ兵庫頭であった。「古くから朝廷が武士を召し置かれるのは、逆臣を退け、勅命に背く者を討つためであります。このように目にも見えぬ妖変のものを討てという御命令は、これまで聞いたこともございません」と申し述べたものの、勅命である以上は従わぬわけにはいかず、命に応じて参内した。
頼政は、頼み切った郎等遠江国の住人・猪早太に、母衣の風切羽で矧いだ矢を負わせて、ただ一人を従えて参内した。自身は、二重の狩衣を着て、山鳥の尾羽で矧いだ鏑矢二本を滋藤の弓に添えて、南殿の大床に参上していた。
頼政が矢を二本手にしていたのは、源中納言雅頼(当時はまだ左少弁であった)が、「変化のものを討つにふさわしいのは頼政であろう」と推挙したためである。もし第一の矢で射損じたのなら、第二の矢で雅頼の首の骨を射抜いてやろう、と心に決めていたのである。
御悩の時刻になると、東三条の森の方から黒雲が一叢、もくもくと立ち上り、御殿の上におよそ五丈ばかり垂れ込めた。頼政がじっと見上げると、雲の中に怪しい影がある。これを射損じたなら、この世に生きてはいられまいと思い、頼政は矢を取り弓に番え、「南無八幡大菩薩」と心の中で祈念して弓を引き絞り、ひょうっと矢を放った。
手応えがあり矢は見事に命中し、頼政は「射得たりやおう!(射抜いたぞ)」と矢叫びを上げた。猪早太がさっと駆け寄り、落ちてきた怪物を押さえつけ、柄も拳も通れ通れと続けざまに九度も刀で切り裂いた。そして上下の人々が手に手に火を灯してその姿を見ると、頭は猿、胴体は狸、尾は蛇、手足は虎のようで、鳴き声は鵺に似ていた。見る者は皆、恐ろしさに身震いし、恐怖は言葉に尽くせぬほどであった。
宮中はどよめき、主上は感激のあまり、頼政に獅子王という名の御剣を下賜された。宇治の左大臣が賜りついで御前の階段の半ば程まで進んだとき、四月十日過ぎの頃で、空に郭公が二声三声と鳴きながら飛び去っていった。左大臣がそれを耳にして、「ほととぎす 名をも雲井にあぐるかな(ほととぎすが鳴きながら空高く飛んでいくように、自分の名も天上(雲の上=宮中)に挙げられたな)」と和歌を詠まれたところ、頼政は右膝をつき、左袖を広げて、月を少し横目にかけながら、「弓張月の入るにまかせて(自然の理に任せたまででございます)」と御剣を賜って退出した。
頼政は弓矢を取って天下に名を馳せただけでなく、和歌の道にも通じた人物であると、当時の人々は感心し、深く感じ入ったという。また、討ち取られた変化の怪物は、うつぼ舟に納められて流されたという。
また、応保年間の頃二条院がご在位の折、鵺という化け物の鳥がたびたび禁中で鳴き、天皇の御心を悩ませることがあった。今度も先例に従って、この頼政が召し出された。この時は五月二十日過ぎ、まだ宵のことであったため、鵺はただ一声だけ鳴いただけで、二声、三声とは鳴かなかった。闇夜のため狙いを定めようにも、姿形は見えず、矢を放つべき的もどこか判然としなかった。
頼政はまず策をめぐらし、最初の矢には大鏑をつがえて、鵺の声がした内裏の上へと射上げた。鵺は鏑矢の音に驚き、しばし虚空に姿を現した。そこで二の矢には小鏑をつがえ、ひいふっと射切ると、鵺と鏑矢は共に目の前へと落ちてきた。
宮中は騒然とし、主上はその功績に深く感動され、頼政に御衣を下賜された。今度は大炊御門の右大臣公能公が賜りついで、昔の名射手養由は雲の彼方の雁を射たが、今の頼政は雨の中で鵺を射たと感心して「五月闇名をあらはせる今宵かな(五月闇の暗い夜であるが、今宵はそなたの名があらわれたな。)」と言葉をかけられると、頼政は「たそがれ時も 過ぎぬと思ふに(老いの身ではございますが。)」と御衣を肩にかけて退出した。
この度の功績に対して重ねて恩賞があり、頼政は伊豆国を賜り、子の仲綱が受領となり、頼政自身は三位として丹波の五箇庄と若狭の東宮川を領知して、安泰に暮らすはずの人物であった。しかし、由なき謀反を起こして以仁王(宮)を失い、自らもその子孫も滅びてしまったことは、嘆かわしいことであった。
→前のお話『宮御最期』
https://morinorijapan.com/tale-of-the-heike/miyagosaigo
▼平家物語現代語訳一覧はこちら
※演奏会や講座等で行う平家物語を現代語訳にしています
https://morinorijapan.com/category/tale-of-the-heike/
ここまでご覧いただきありがとうございました。
いつかどこかでお会いできますように。